この記事は、心電図検定に向けて12誘導心電図を勉強している医療者の方に向けて書いています。
基礎を一通り学び終え、
- 12誘導心電図ってどう読み解けばいいのか?
- なぜこの波形になるのか?
という、少し深いところまで理解しておきたい方に向けて、
杉山裕章先生の名著『心電図の読みかた、考えかた』をもとに、
臨床と検定対策の両方に役立つ知識を、わかりやすくお伝えしていきます。
心電図検定や12誘導の勉強を進めていくと、
**「低電位(QRS波が小さい状態)」**というテーマに出会います。
その代表的な原因として登場するのが、甲状腺機能低下症です。
でも…
「なんで甲状腺機能の低下と、心臓や心電図に関係あるの?」
──そんなふうに、知識がゼロの状態では疑問だらけなのも当然です。
この記事では、
「甲状腺って何者?」「どうして心電図が変わるの?」というところから、
臨床と検定の両方に役立つ視点で、やさしく紐解いていきます。
目次
甲状腺機能低下症とは?
甲状腺は、首の前側(のどぼとけの下)にある小さな臓器で、
「T3(トリヨードサイロニン)」「T4(サイロキシン)」という代謝ホルモンを出しています。
このホルモンは、体のエンジンを回す存在。
だから、分泌量が落ちると──
体全体が**スロー運転モード(省エネ状態)**になってしまうんです。
スロー運転モードになるとどうなる?
- 疲れやすくなる
- 脈が遅くなる(洞性徐脈)
- むくみやすくなる
- 顔がむくみ、表情がぼんやり
- 皮膚がカサカサ
- 便秘、寒がり、うつっぽい など
むくみの正体は「ヒアルロン酸」だった!
甲状腺ホルモンが足りなくなると、
体の中では「ムコ多糖類(ヒアルロン酸・コンドロイチンなど)」という物質が分解されずに溜まります。
これらはもともと「うるおい」や「関節のクッション」を保ついいやつですが…
代謝が落ちて分解されずにどんどん溜まり、
水を引き寄せまくり、結果として“むくむ”!
というわけです。
ムコ多糖は悪者?
いえ、もともとはとても大切な成分です。
以下に「良い働き」と「溜まりすぎたときの影響」をまとめました。
【ムコ多糖の特徴】
- ヒアルロン酸:保湿・関節保護に役立つが、過剰にたまると「むくみ」や「心嚢液」の原因になる
- コンドロイチン硫酸:軟骨の弾力を保つが、過剰にたまると水分を抱え込んで「浮腫」につながる

ヒアルロン酸もコンドロイチンも、もともとは良い子たちなのよ?
でもね、バランス崩れるとすぐ水ためちゃうの…代謝ってホント大事〜!
むくみは心臓にも…心嚢液がたまる!
ムコ多糖が心臓の周囲にたまると、
心嚢(心臓を包む膜)の中に水分が蓄積されます。
この液体は「血」ではなく、水分を多く含んださらっとした滲出液です。
→ 徐々にたまることで、慢性的に心電図に影響を与えます。
心電図に現れる変化はこれ!
【甲状腺機能低下症における心電図所見とその理由】
- QRS低電位 → 心嚢液や全身のむくみによって電気信号が皮膚に伝わりにくくなるため
- 洞性徐脈
→ 甲状腺ホルモンが不足して心拍数が落ちる(スローモードになる) - T波の平坦化・陰性化
→ 心筋の再分極が弱くなり、波形が小さくなる - QT延長
→ 再分極に時間がかかり、QT間隔が延びる
今回のまとめ
【甲状腺機能低下症と心電図のつながり】
- 病態:甲状腺ホルモンが不足し、全身の代謝が低下する
- むくみの原因:ムコ多糖類(ヒアルロン酸・コンドロイチンなど)が分解されず、水分を引き寄せて組織に蓄積する
- 心臓への影響:心嚢液が徐々にたまり、電気伝導が妨げられる
- 心電図で見られる変化:QRS低電位、洞性徐脈、T波平坦・陰性化、QT延長など
おわりに
今回は、**「なぜ甲状腺機能低下症で心電図に変化が出るのか?」**をテーマに、
体の仕組みからじっくり見ていきました。
波形の背後にある「代謝」「むくみ」「ホルモン」の関係を知っておくと、
心電図がただのグラフではなく、“体の声”として読めるようになります。
今回はここまで!おつかれさまでした〜
完璧じゃなくていいんです。ゆっくり覚えていきましょう!





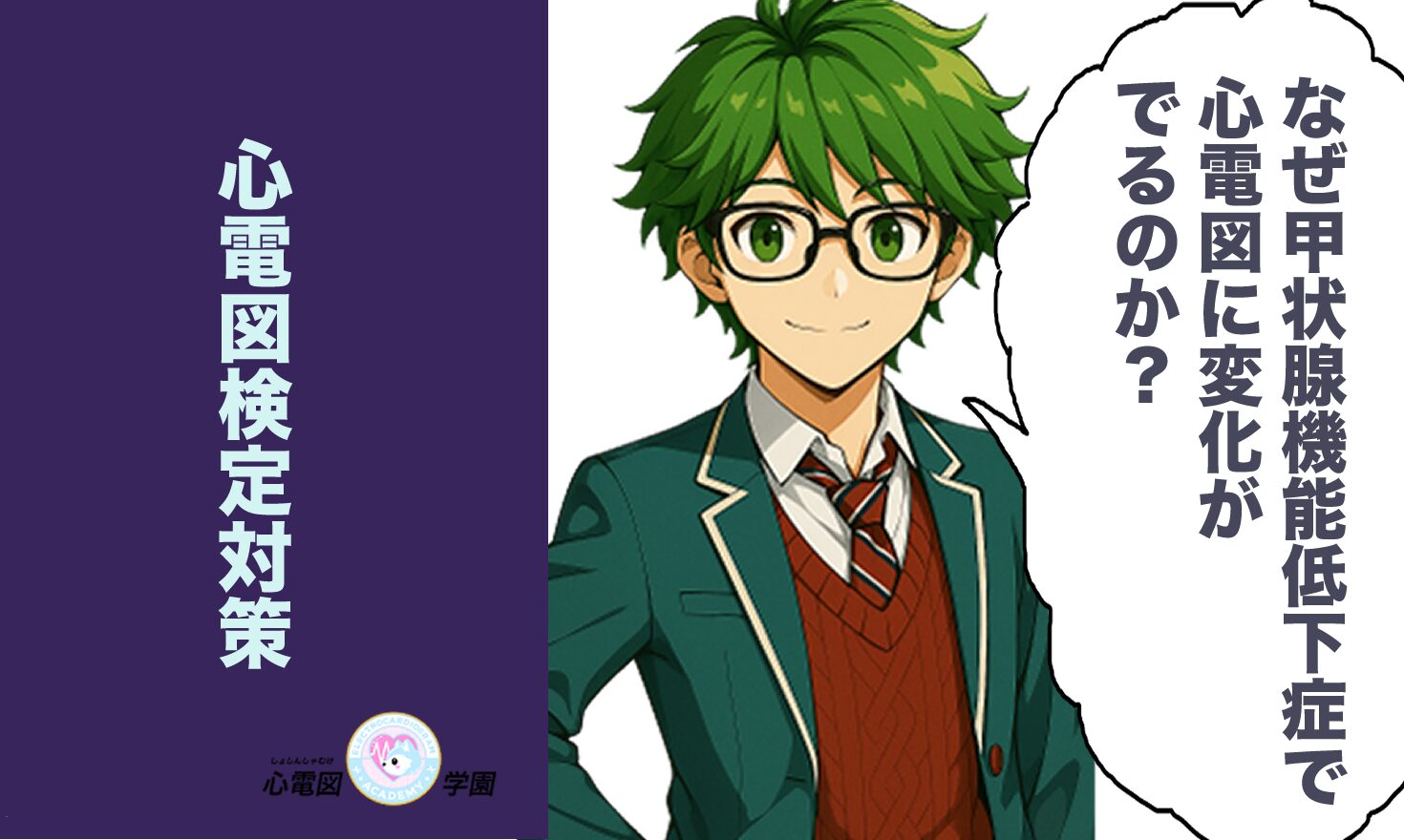


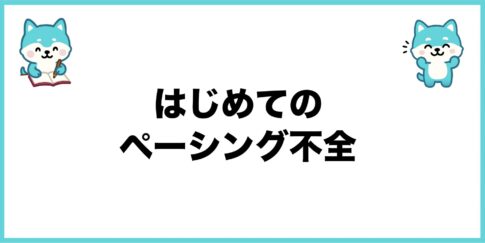
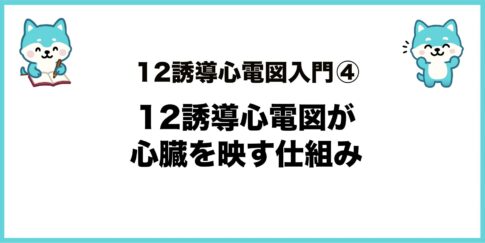
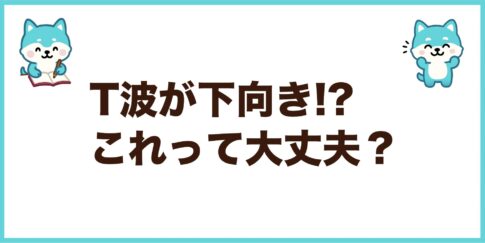
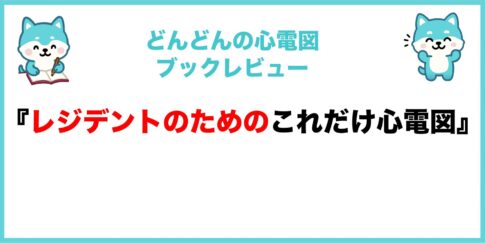
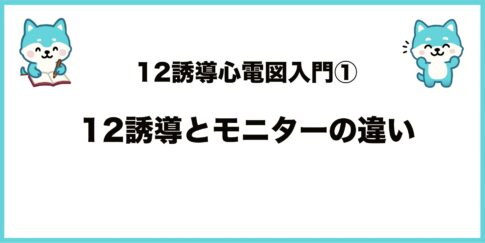
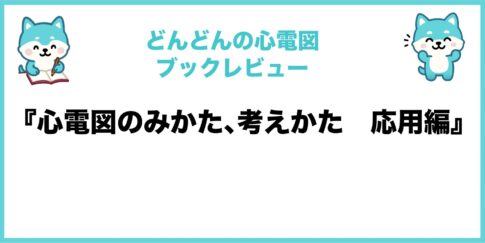
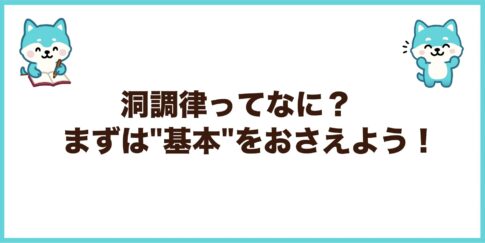
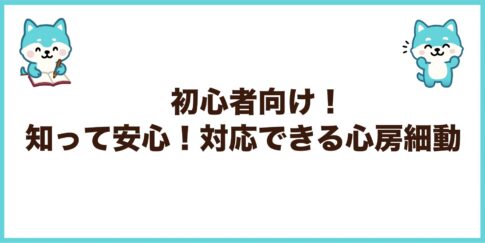
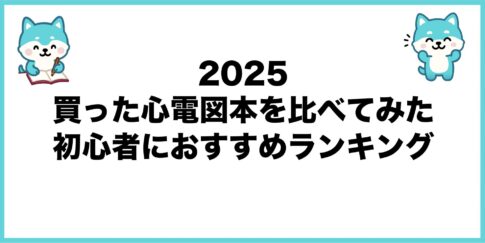
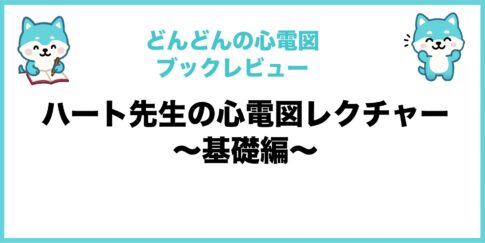
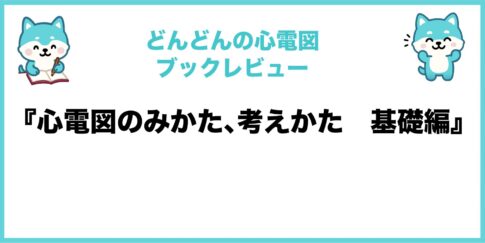
こんにちは!
循環器ナース歴9年目、看護師歴12年目のどんどんです!