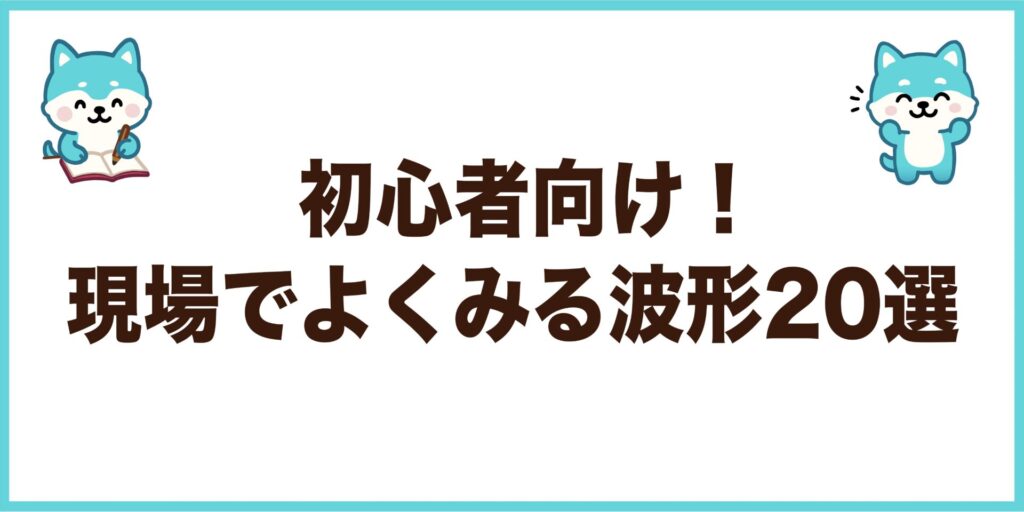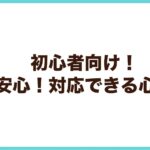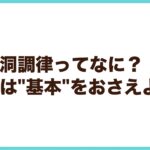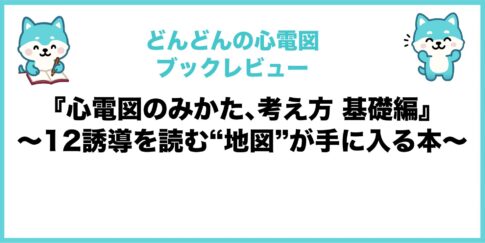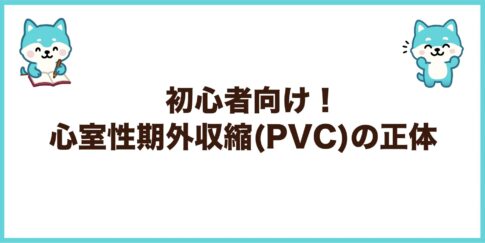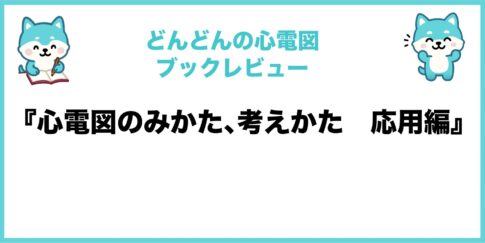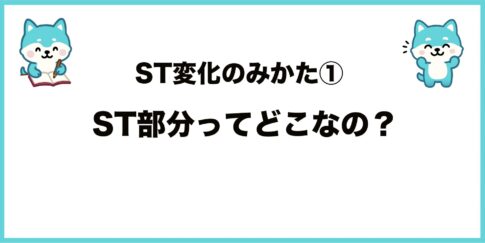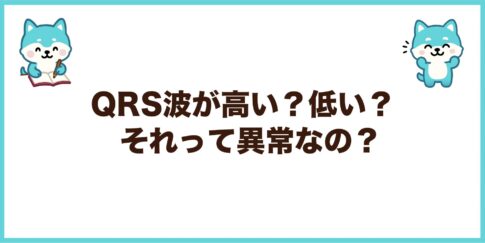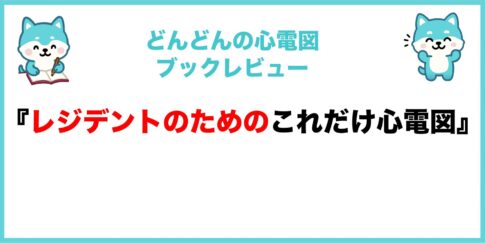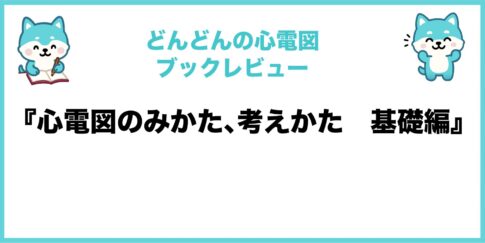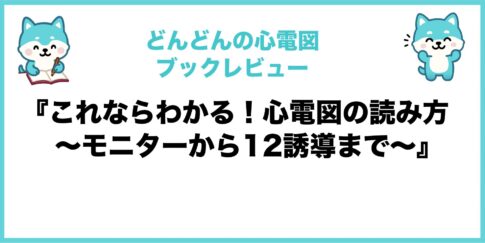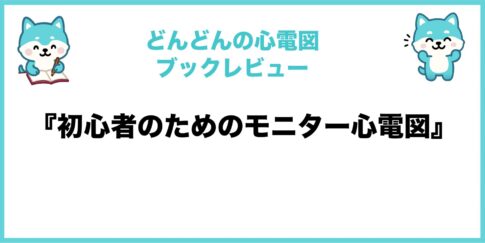こんにちは〜!
看護師歴12年目、循環器ナース9年目のどんどんです!
いまも一般病棟でバリバリ働いてます!
このブログは、
心電図が苦手…もう苦手すぎてどこから手をつけたらいいのか分からない…
そんな看護師さんに向けて書いています!
◆ 心電図の勉強、最初に思うこと
心電図の勉強を始めようとすると、こんなふうに思いませんか?
- 何から勉強すればいいの?
- 参考書は買ったけど、難しすぎて最初の数ページだけで止まってる…
- 結局、何個覚えれば現場の波形が読めるの?
- 誰かゴールを先に教えてほしい!
めちゃくちゃ分かります。
私も、ほんとに同じこと思ってました。
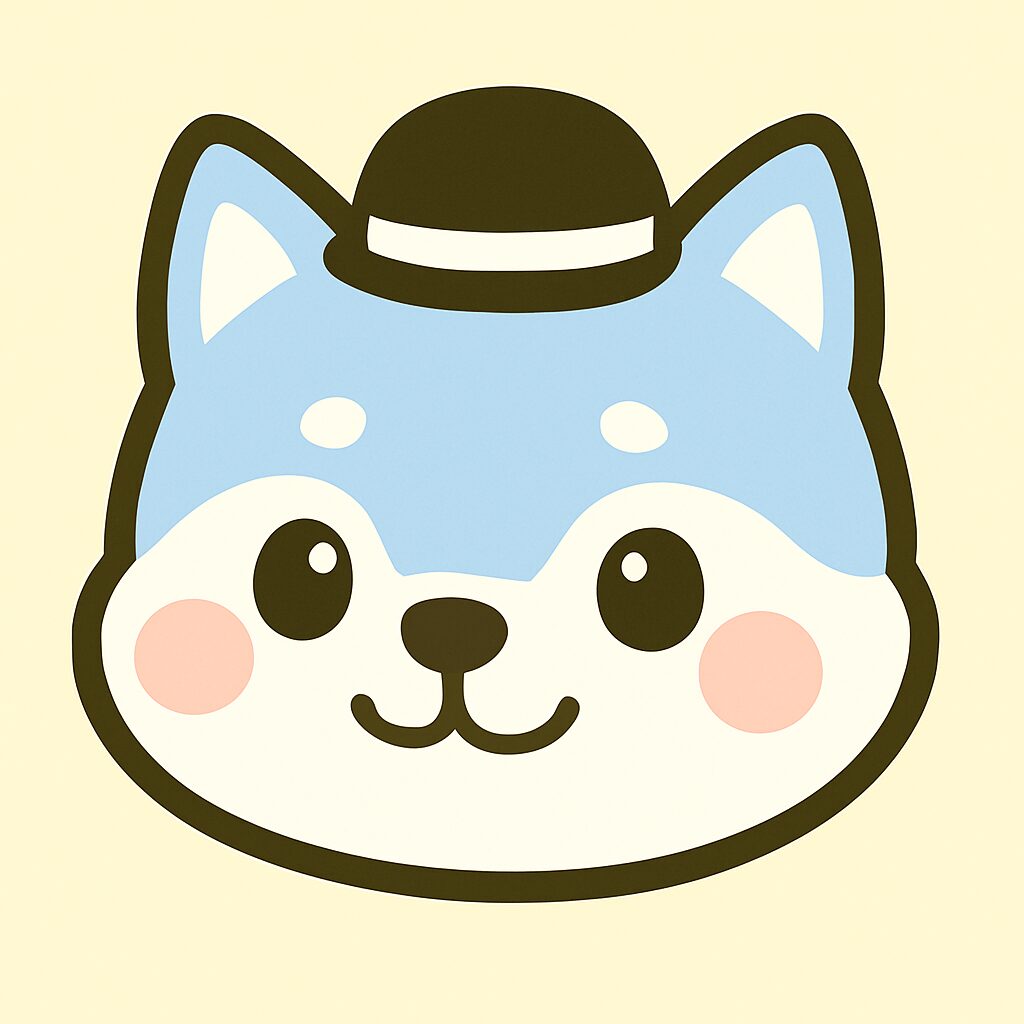
とりあえず参考書を買って満足して、中身はほぼ読んでませんでした…(笑)
でも大丈夫。この記事では、そんな疑問を解決していきます。
一緒にゆっくり頑張っていきましょう!
目次
- まずは結論、現場でよく見る波形は20種類
- STEP1|洞調律(どうちょうりつ)〜まずは基本の波形を覚えよう〜
- STEP2|よく見る不整脈を覚えよう
- STEP3|緊急波形を覚えよう
- 覚えたあとの進め方
- 今日のまとめ
まずは結論、現場でよく見る波形は20種類
参考書を開くと、心電図波形が50種類くらいびっしり書いてあって、
「えっ、どこまで覚えればいいの?」って、最初から不安になりますよね。
でも、安心してください。
実際に一般病棟や急性期の現場でよく見る波形は、20種類ほどなんです。

じゅ、20種類か〜…それでも多く感じちゃうよ〜。ちゃんと覚えられるかなあ…?

大丈夫です。波形の中にも優先して覚えるべきものがあるんです。
最初に覚えるのは、その中でも特に大事な8個だけなんですよ!
では、その8つの波形をどう覚えていけばいいのか?
順番に3ステップに分けて紹介します!
『よく見る20波形って何?』という方は、まずはこちらの記事をご覧ください。
STEP1|洞調律(どうちょうりつ)〜まずは基本の波形を覚えよう〜
まずは「正常な波形=洞調律」から!
この波形を見慣れておくことで、
「これは普通」「これは違う(不整脈かも?)」という判断がしやすくなります。

え〜、一番最初に覚えてもらえるなんてずるい〜!人気キャラじゃん!

まずは基本が大事ですからね。僕を見慣れておけば、不整脈の違和感にもすぐ気づけますよ!
STEP2|よく見る不整脈を覚えよう
次に覚えるのは、現場でとにかくよく出る4つの波形です。
- 心房細動(AF)
- 心房性期外収縮(PAC)
- 心室性期外収縮(PVC)
- ノイズ(アーチファクト)
「なんか変だな?」と思ったときに出てきやすいのがこのあたり。
落ち着いて見分けられるようにしておきましょう!

やっと私が入ってる〜!…ちょっと嬉しいかも!

この5波形を判別できれば、心電図の95%以上がわかるようになりますよ!
STEP3|緊急波形を覚えよう
最後は、命に関わる“急変系”の波形です。
- 心室頻拍(VT)
- 心室細動(VF)
- 心停止(Acystole)
この3つを見逃さなければ、
急変対応に強くなれます!

…なんかもう、名前からして怖いんだけど!?

たしかに怖いですが、ちゃんと覚えれば落ち着いて対応できます。
ここが看護師としての“かっこいいポイント”ですよ!
覚えたあとの進め方
この8つの波形を“なんとなく”覚えられたら、
もう心電図の基礎はほぼOK!
あとは、現場で波形を見かけたときに
「これってブログで見たやつかも!」と振り返っていけば、
少しずつ理解が深まり、自信につながっていきます。
残りの12波形は、
必要になったときにゆっくり覚えていけば大丈夫です。
今日のまとめ
- 参考書にある心電図は50種類以上。でも現場でよく見るのは約20種類。
- 特に重要なのは8波形だけ。
- 覚える順番は、①洞調律 → ②よく見る不整脈 → ③緊急波形の3ステップ
- この8つが分かれば、現場の波形の95%は見分けられる!

8個でいいなら…なんとかなるかも!ちょっとだけ希望見えてきた〜

焦らず、一歩ずつ覚えていけば大丈夫ですよ。
今日のところはここまで。おつかれさまでした!
完璧じゃなくてOKです。
ひとつずつ、ゆっくり覚えていきましょうね!