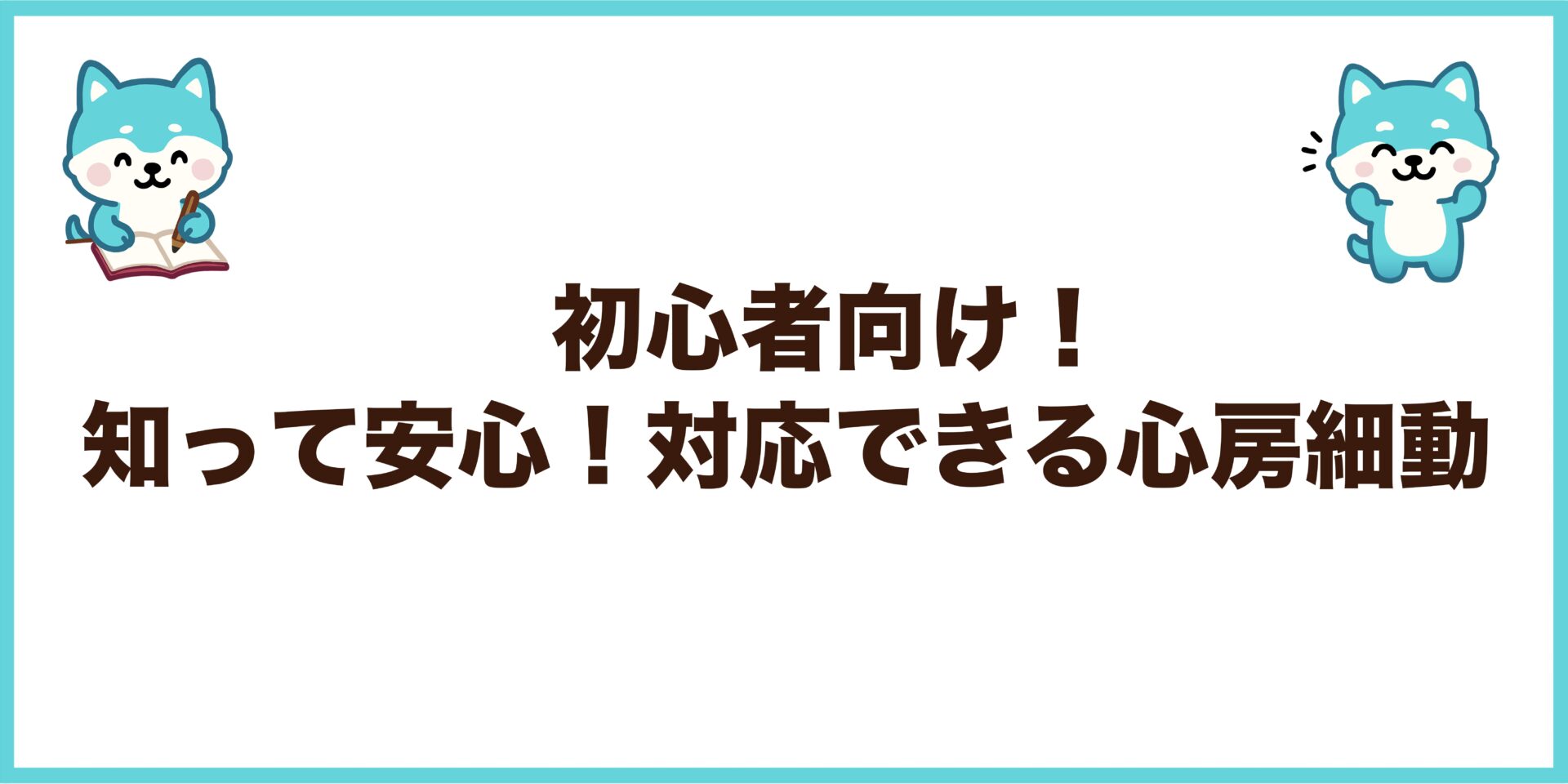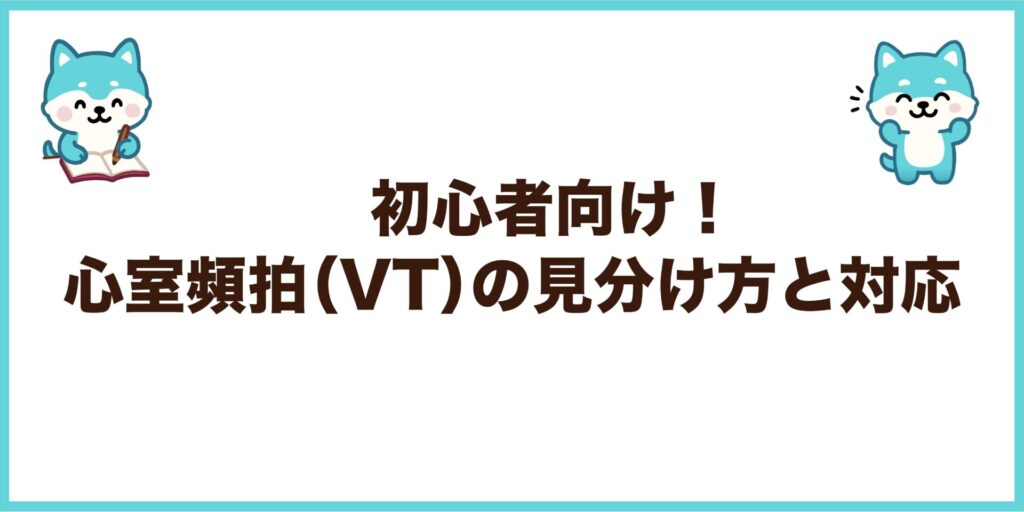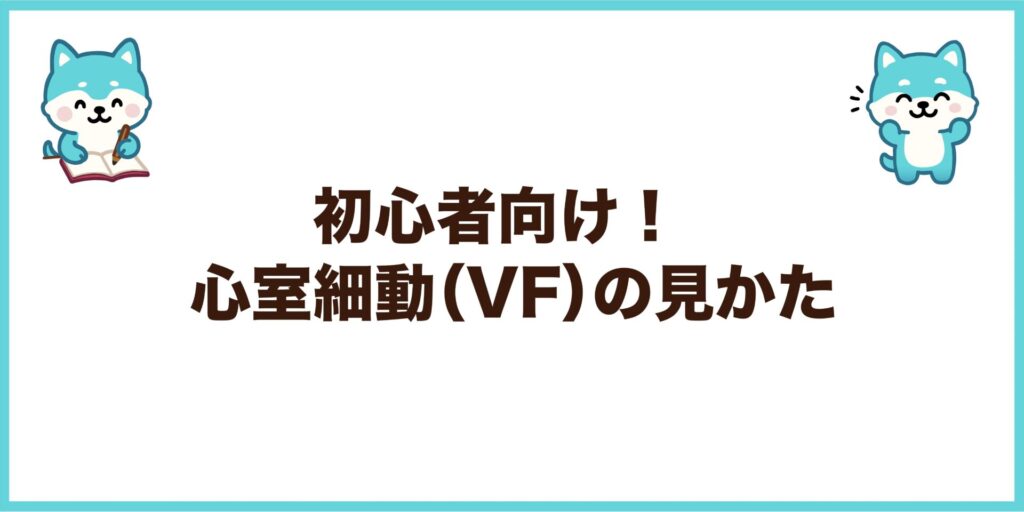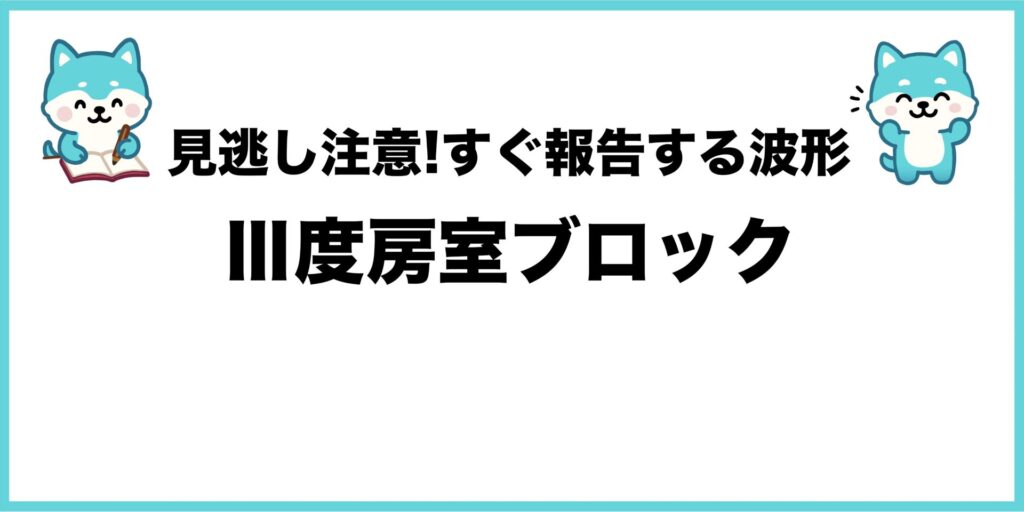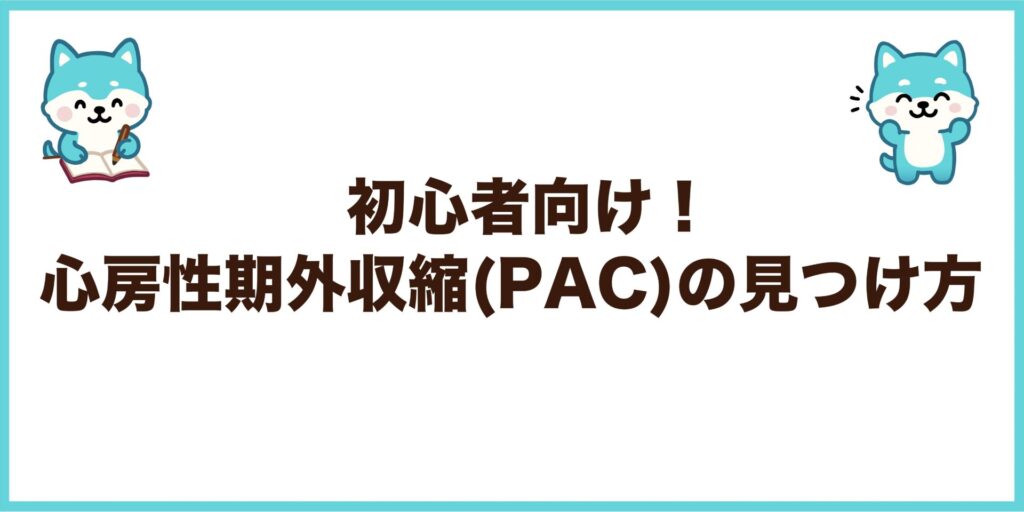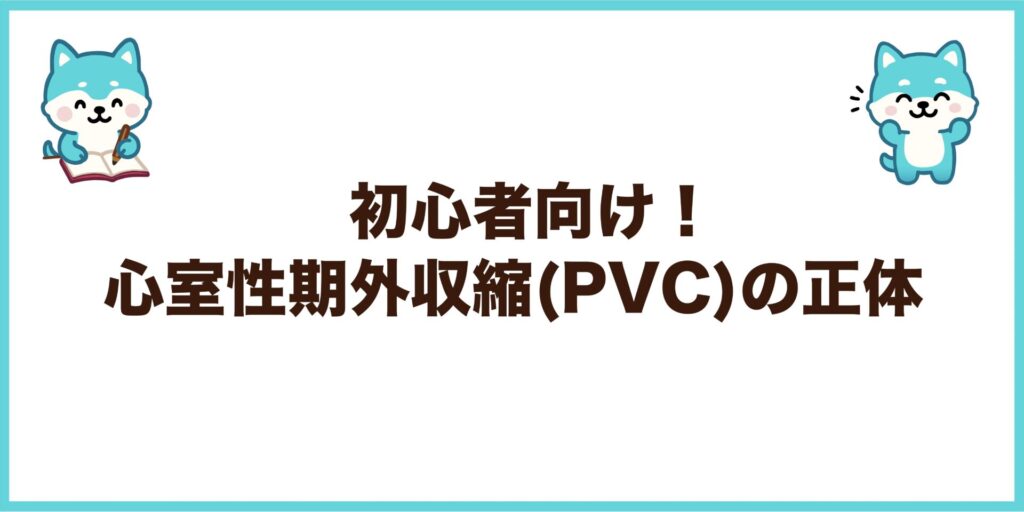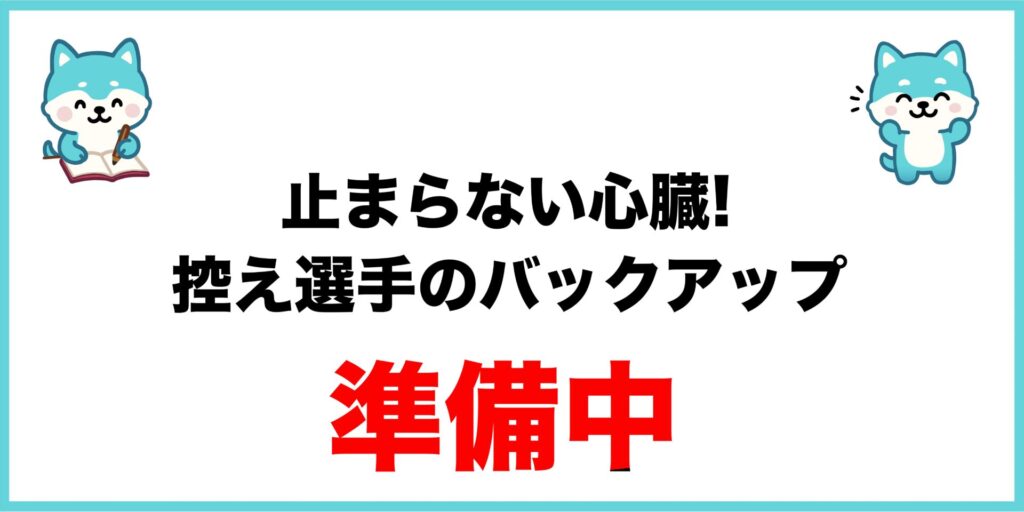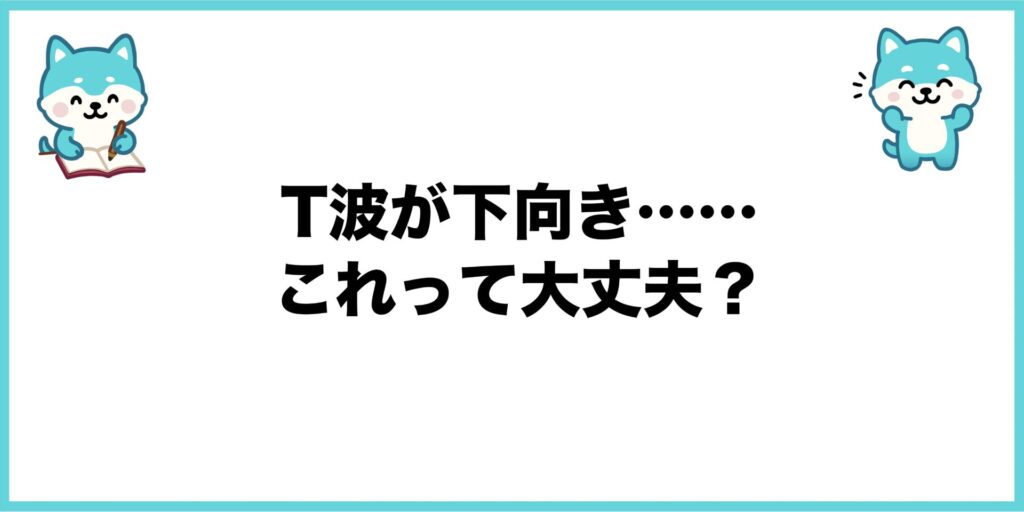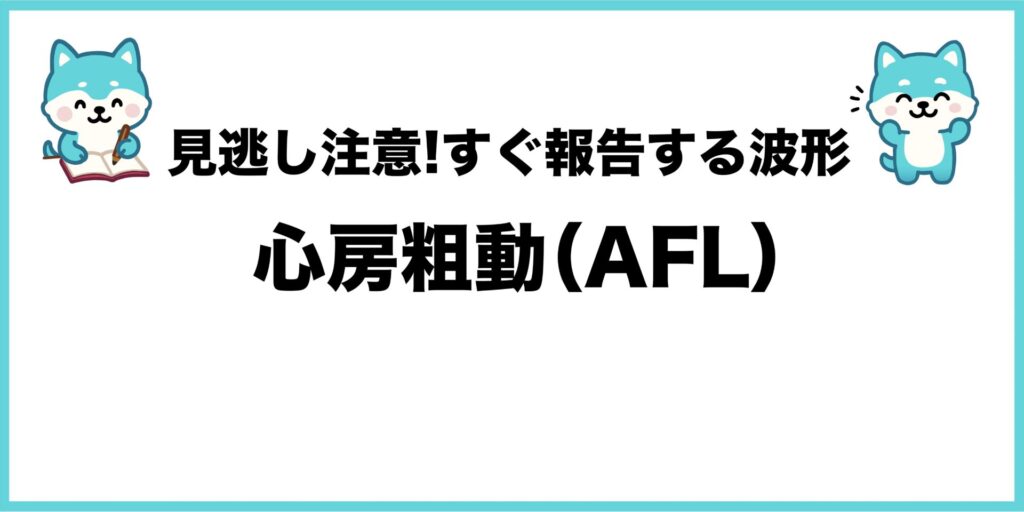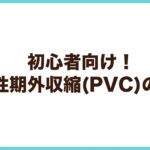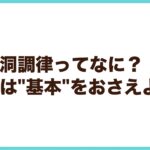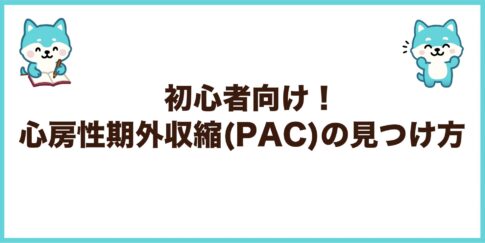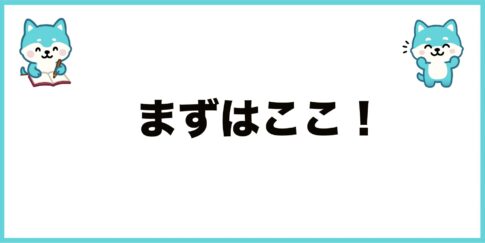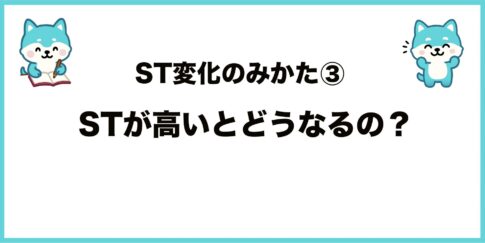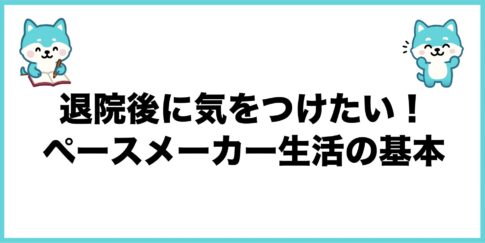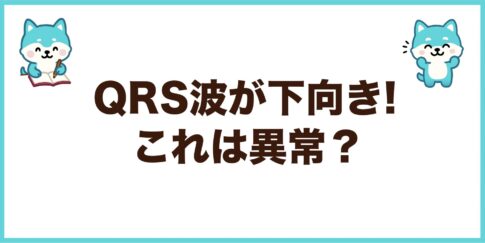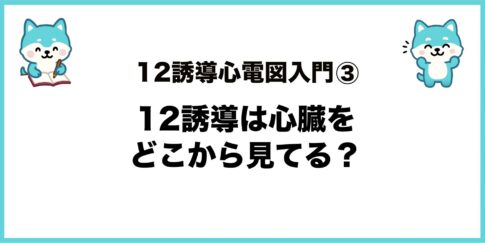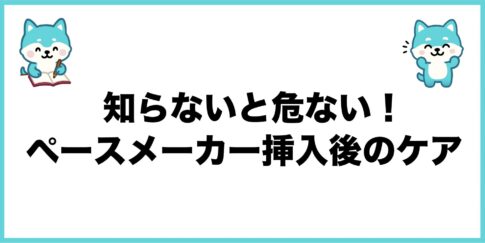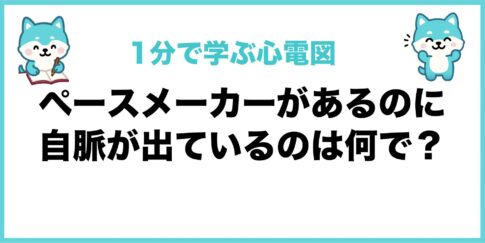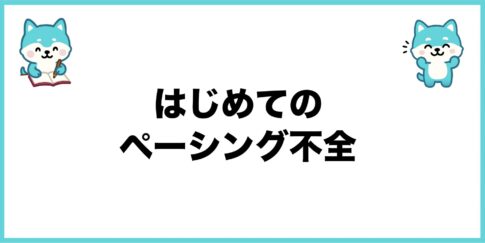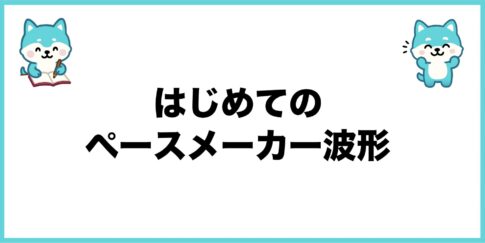循環器ナース歴9年のどんどんです。
このブログは、
- モニター心電図に自信が持てない看護師さん
- 心電図の勉強がなかなか続かなかった看護師さん
- 現場で役立つ心電図を学びたい看護師さん
のためのブログです。
この記事では、
心房細動の基本から見分け方までを、やさしくまとめています。
まずは、心房細動を見分けるための大事なポイントを3つだけ、
サクッと確認していきましょう。
気になったところがあれば、
無理のないペースで、その後の項目も見てみてくださいね。
目次
心房細動を見つけるポイントはこの3つ
心房細動は、心臓の上の部屋である心房が細かく震えるように動いてしまう(細動)ことで、
心臓の司令塔である洞結節からの指示がうまく伝わらず、
心臓のリズムがバラバラで不規則になってしまう不整脈です。
心房細動を判別するには、まずこの3つのポイントをチェック!
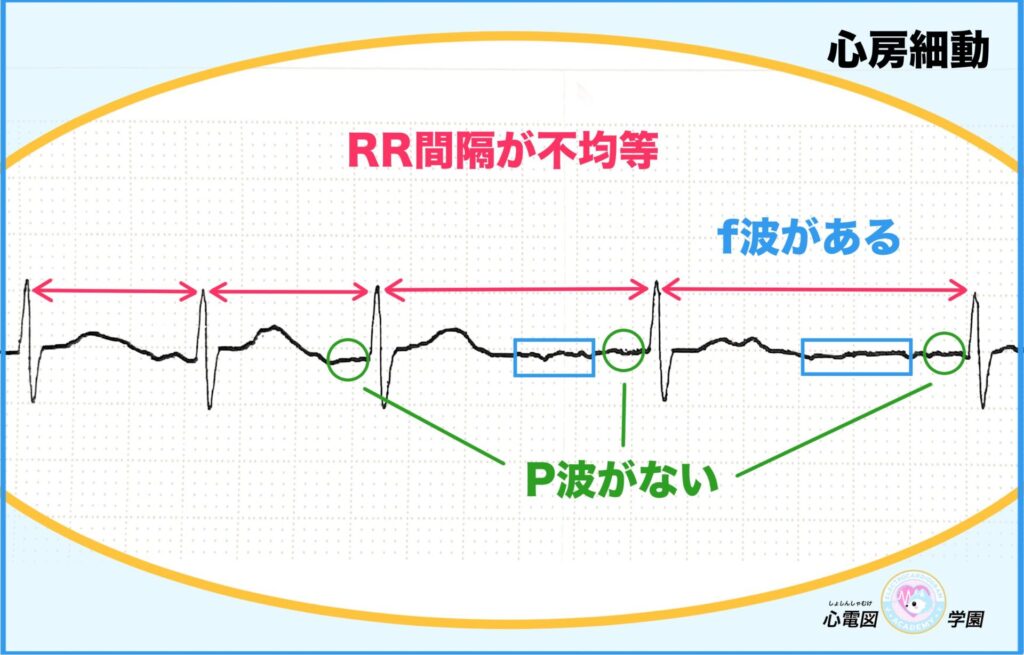
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| P波が見えない | QRS波の前にあるはずのP波が見えない |
| RR間隔がバラバラ | QRS波とQRS波の間隔がそろっておらず、不規則 |
| f波が見られることがある | 基線が細かく震えて見えることがある |
👉 特に重要なのは「P波が見えない」ことと「RR間隔がバラバラ」なこと。
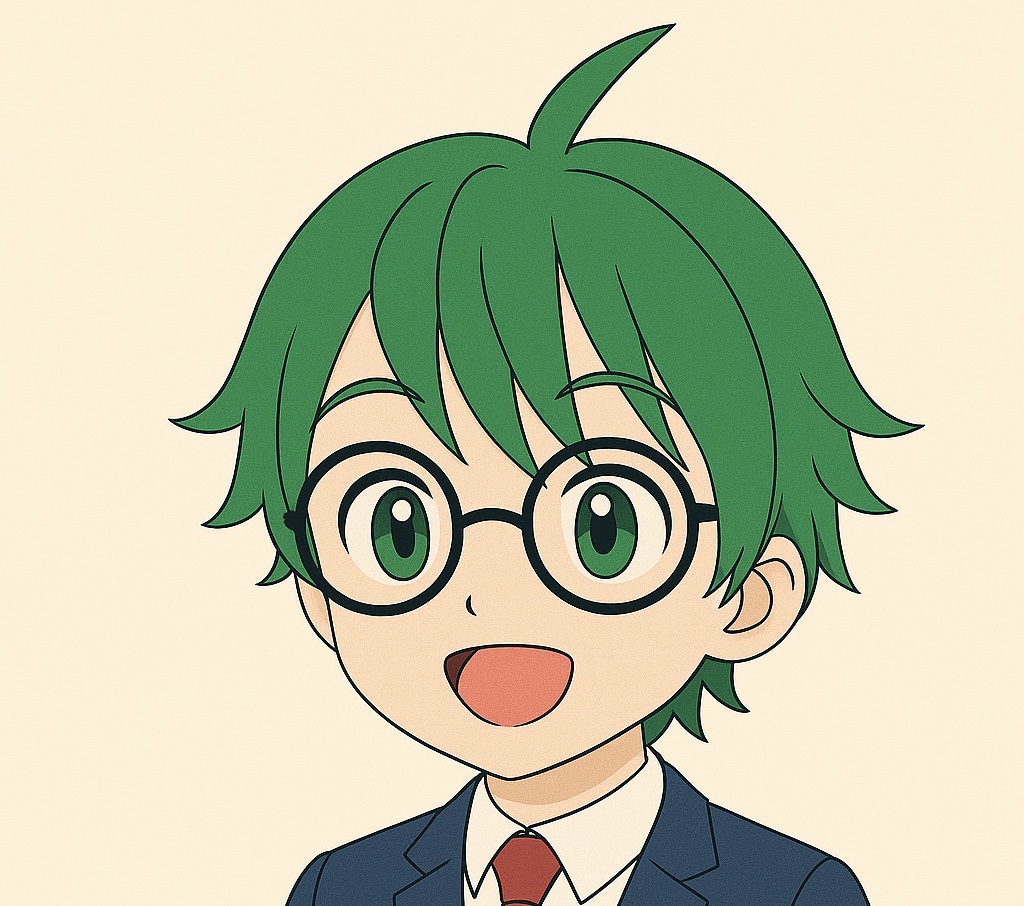
f波は必ず見えるわけではないため、補助的な所見として考えます。
P波に見える“何か”があっても安心しないで!
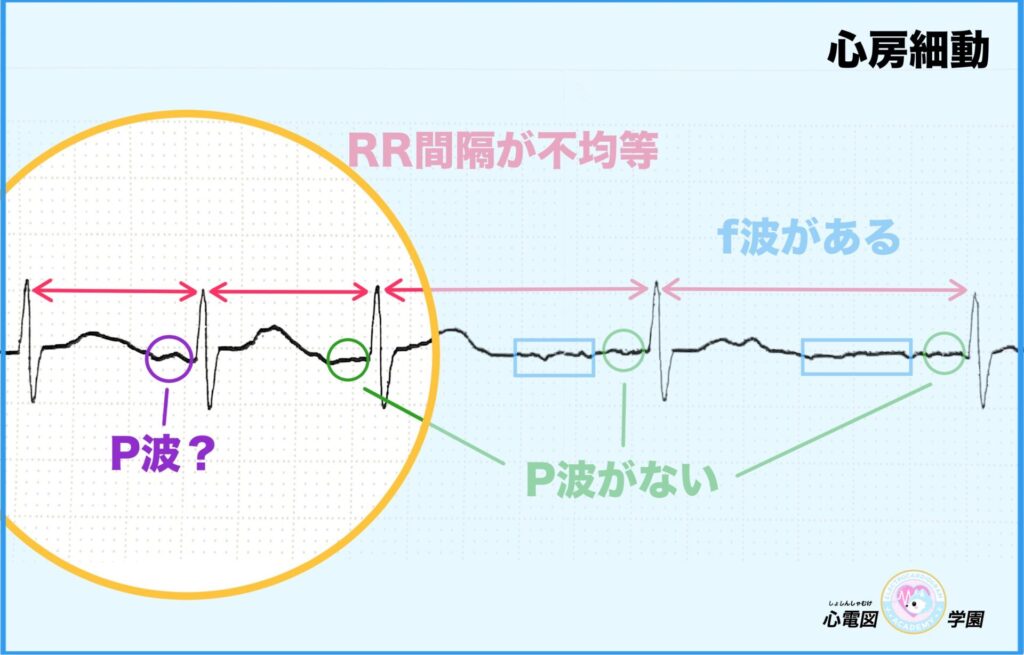
心房細動なのに、
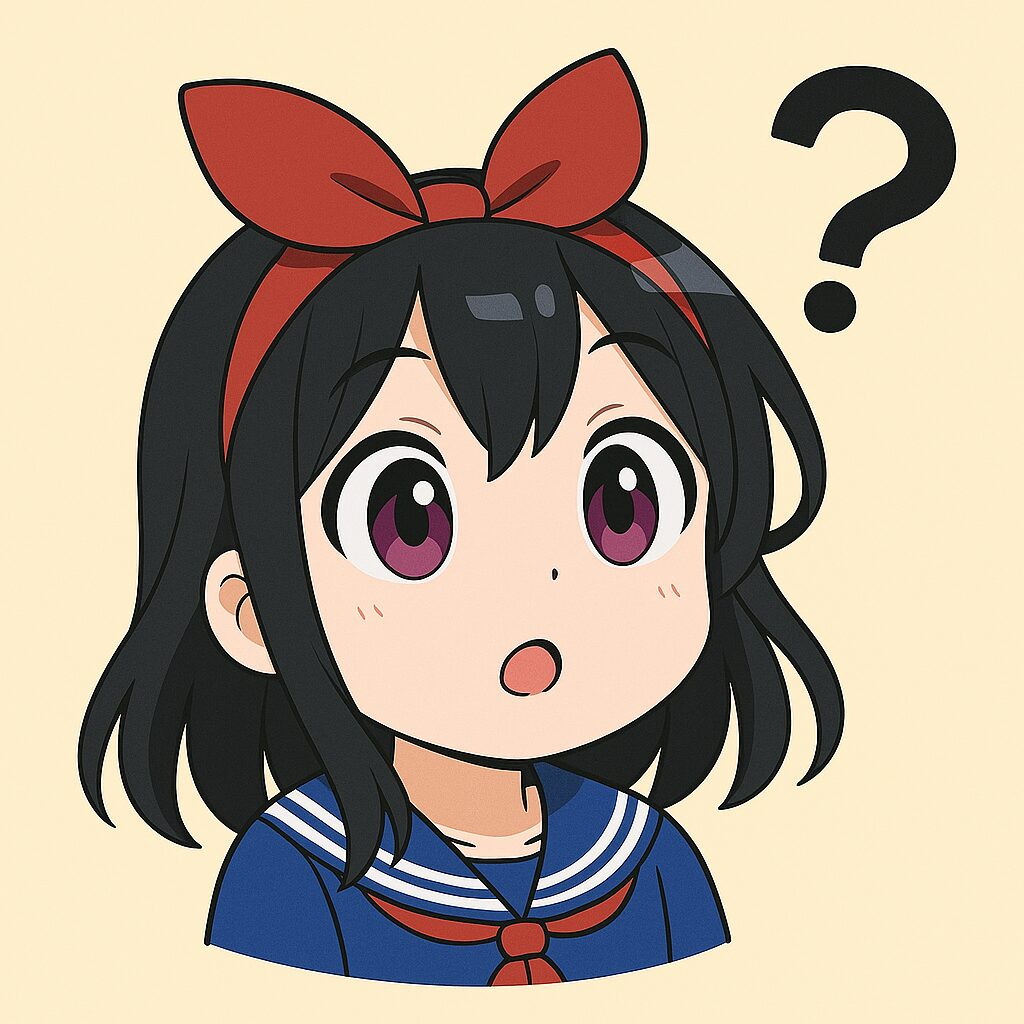
あれ?P波っぽいのがあるような…?
と思うこともあります。
でもそれ、実はP波ではなくf波(細動波)の一部かもしれません!
心房細動は、心房が細かく震えるため、
基線がもやもやして見えます。
ときには、P波のように見えるf波が混じることもあります。
そんなときは、“P波っぽいから洞調律だ!”と早とちりせず、
「RR間隔がバラバラじゃないか」「PQ間隔は毎回そろっているか」も合わせて確認しましょう!
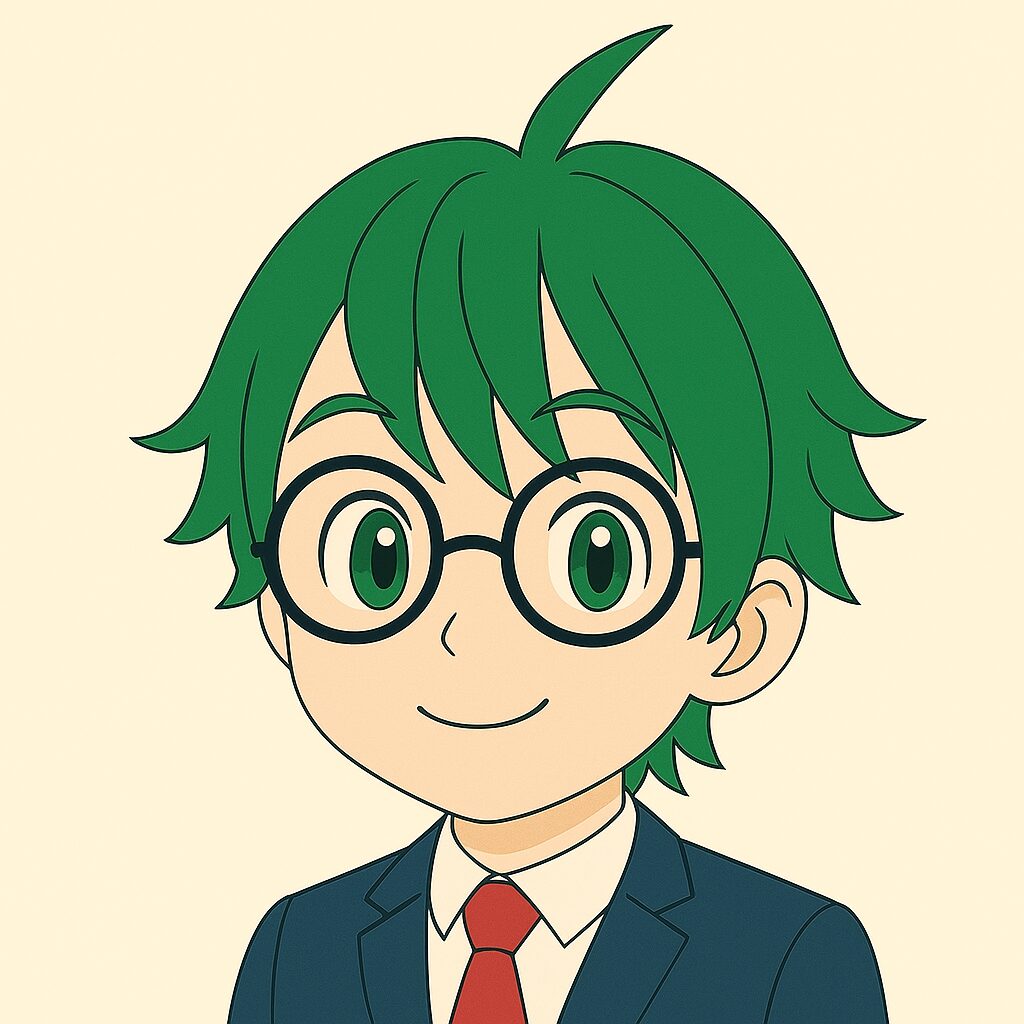
見た目だけで決めつけると、見落としにつながりますよ!
“リズムの乱れ”にもちゃんと目を向けてくださいね。
心房細動はどのくらい多いの?
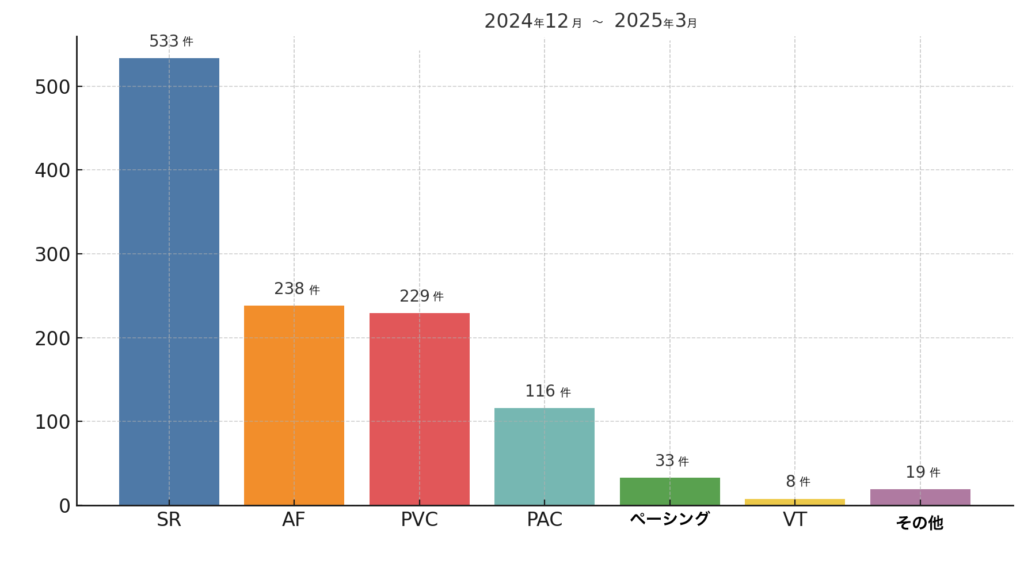
心房細動は、現場で洞調律の次に多く見られる波形です。
実際、2024年12月から2025年3月までのモニター波形の統計を取ると、
約20%前後が心房細動でした。
つまり、心房細動を読めるようになれば、
「波形が読めるようになった!」と感じられるチャンスがぐんと増えます。
心房細動になると何が悪いの?
心房細動は、
「心電図がちょっと乱れているだけ」
…ではありません。
心房細動になると、
心臓の中で、トラブルの芽が少しずつ育っていきます。
① 血栓ができやすくなる
心房がプルプル震えるせいで、
**血液が滞り、血栓(血のかたまり)**
ができやすくなります。
② 血栓が飛んで重大な合併症に
- 脳に飛べば → 脳梗塞
- 肺に飛べば → 肺塞栓
命に関わるトラブルを引き起こす可能性があります。
③ 心臓のポンプ機能が下がる
心房がうまく働けず、心室に血液を送り出せないため、
全体として心臓の働きが約20%低下してしまうとも言われています。

うわ…血栓って、あの血のかたまりのことだよね?それが脳とか肺に飛んじゃうなんて…怖すぎる…!
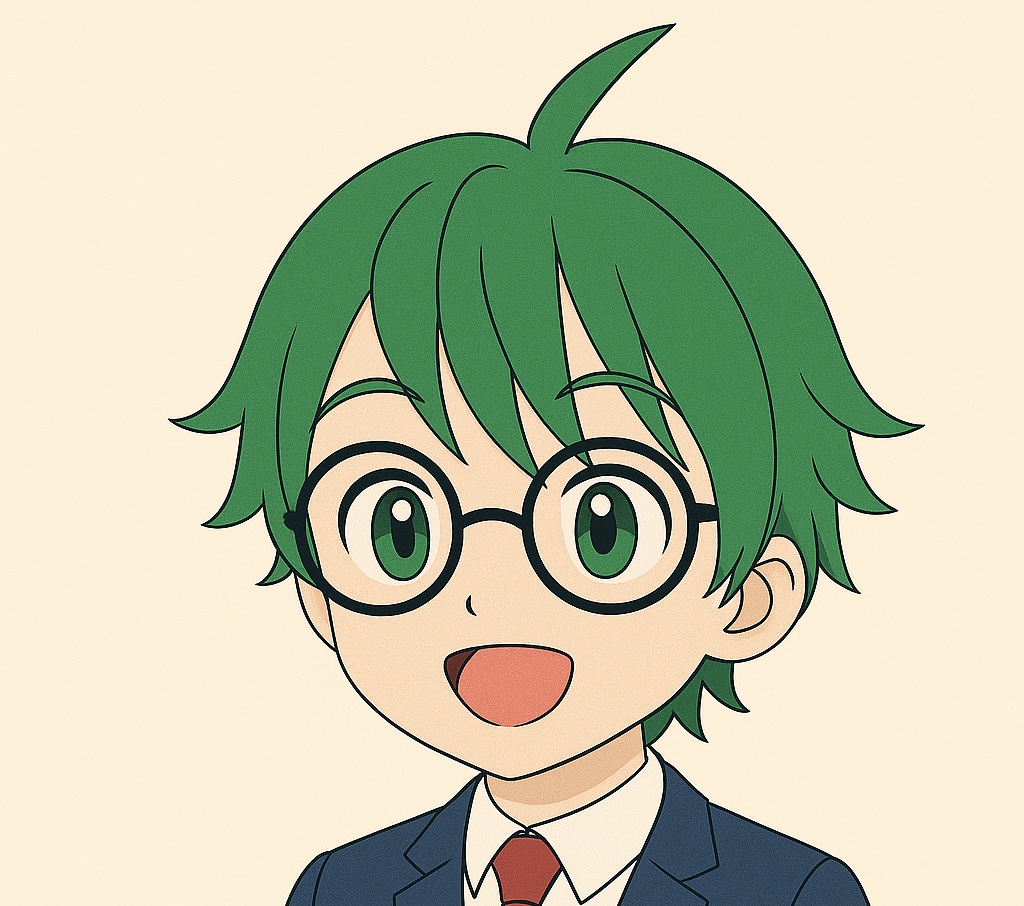
心房細動は“見つけて終わり”じゃなくて、“見つけたら即対応”が鉄則だよ。
心房細動を見つけたらどうする?
モニターで心房細動(AF)らしき波形を見つけたときは、
慌てずに、次の流れで確認・対応していきましょう。
① まず確認すること
- 抗凝固薬を内服しているか?
- これまでも心房細動(AF)があったか?
これまでも心房細動(AF)があり、
すでに抗凝固薬を内服している方であれば、
慌てて対応する必要はありません。
「急に出現した」場合は要注意!!
これまで洞調律だったのに、
急に心房細動(AF)になった場合は、
👉 抗凝固薬を内服していないことが多く、血栓形成リスクが高いため、必ず報告と対応が必要です。
② 症状の有無をチェック
次に、患者さんの状態を確認します。
- 胸の不快感はないか
- 息苦しさはないか
- 意識レベルに変化はないか
あわせて、以下のバイタルサインを測定します。
- 血圧の低下
- 脈拍の変化
- SpO₂の低下
- 話しづらさ、手足の動かしづらさ
③ 医師に報告する内容
報告するときは、次のポイントをまとめて伝えましょう。
- 心電図の特徴
(P波なし、RR間隔が不規則 など) - バイタルサイン
- 症状の有無
- 今後、治療を開始するかの確認
④ 治療の基本は「血栓を作らせないこと」
心房細動の治療で、まず大切なのは
血栓を作らせないことです。
そのため、
- 抗凝固薬
(ワーファリン、リクシアナなど) - ヘパリンの点滴
が選ばれることが多いです。
状況によって行われる治療
患者さんの状態によっては、
- 心拍数をゆっくりにする薬で脈を落ち着かせたり(ワサランなど)
- 元のリズムに戻す治療(アブレーション)
が行われることもあります。
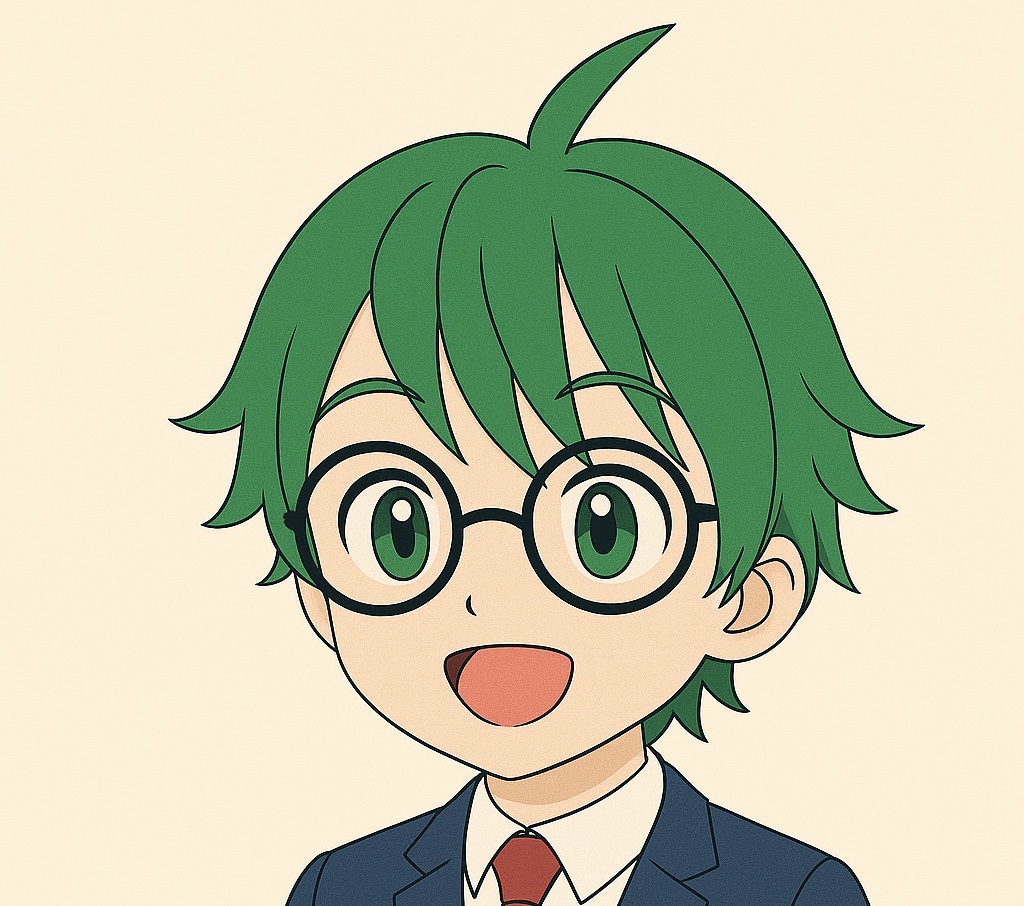
心房細動で大事なのは、
“血栓を作らせない視点”を忘れないことだよ。
心房細動をおさらい
- 心房細動は洞調律の次に多く、全体の約20%
- 見つけるポイントはこの3つ:
① P波がない
② RR間隔がバラバラ
③ f波が見えることもある(でも①②が大事) - 放っておくと…
血栓 → 脳梗塞・肺梗塞のリスク
→ 心機能が低下して全身に影響が出ることも - 見つけたら
慢性か新規かを確認 → 症状&バイタル → 医師に報告
基本は血栓予防の薬+必要に応じてリズム調整

よし!心房細動の見つけ方と対応、覚えたよ!
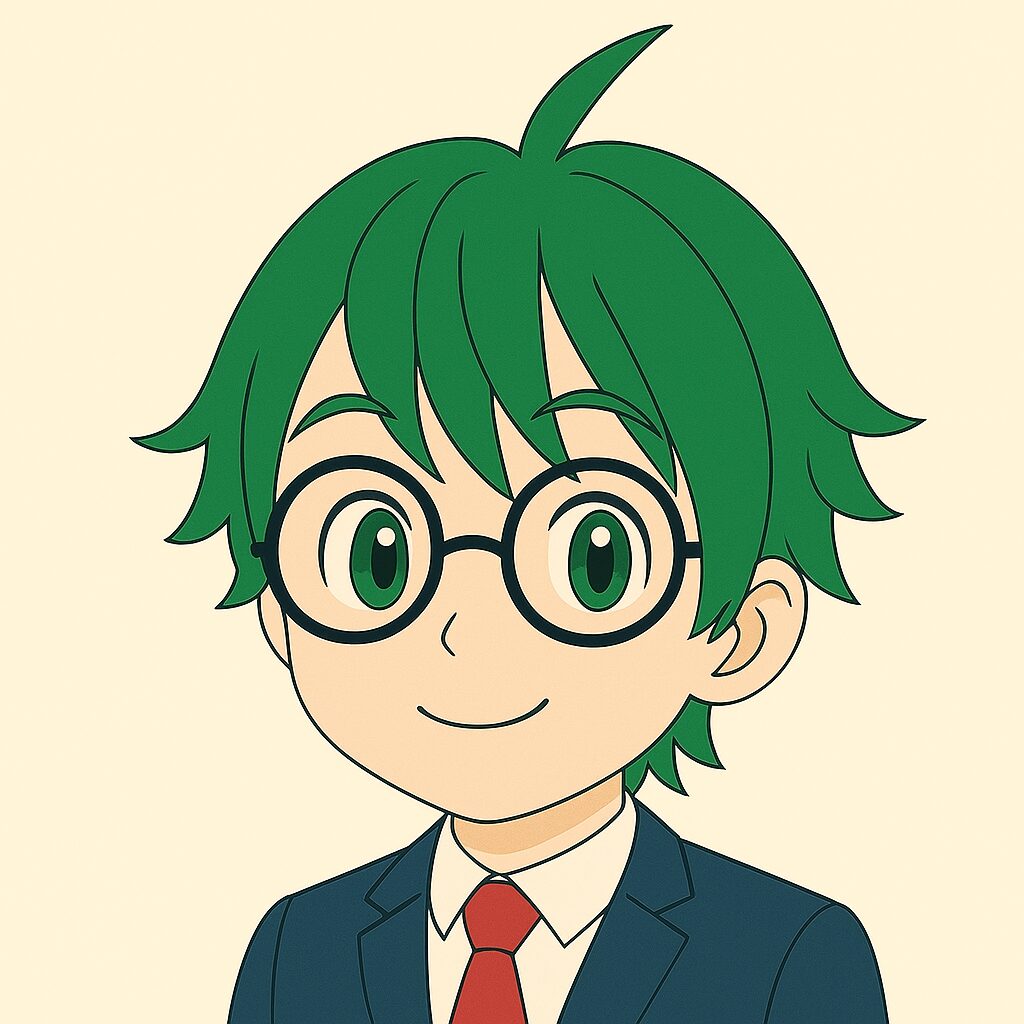
うん。“見つけたらすぐ動く”が大事だよ。
心臓手術後は心房細動が起こりやすい!
・心臓手術後は心房細動が出やすい
・術後心房細動は珍しい合併症ではない
実際に、
『胸部外科手術における術後心房細動』(横田泰佑,2018年)でも、
「術後にAFが出ることは珍しくない」と報告されているんです。
心臓手術後の
👉 約3人に1〜2人(30〜50%)が心房細動を発症
さらに
CABG(冠動脈バイパス術)後の
👉 約7人に1人〜3人(15〜40%)で心房細動を発症
弁膜症手術を同時に行った症例
👉約2人に1人以上(60〜70%)と、さらに高率に発症
「えっ、そんなに?」と思うかもしれませんが、
それくらい術後AFはよくある出来事なんですね。
術後心房細動が起こりやすい時期
術後の心房細動は、
術後数日たってからも出現することが多い
という特徴があるんです。
- 発症のピーク:術後2日目
- 約70%が術後4日目までに発症
- 約94%が術後7日目までに発症
実際に病棟で働いていると、
集中治療室から一般病棟へ出てくるのは、
術後3〜4日目くらいが多かったのですが、
術後7日目くらいまでに、
「心房細動になることが多いな〜…」
と感じることが何度もありました。
- 点滴が減ってくる
- 歩けるようになり、食事も再開
- 「ひと段落したかな?」という雰囲気になる
つい安心しがちな時期ですが、
モニター波形の変化を見逃さない意識が
とても大切です!
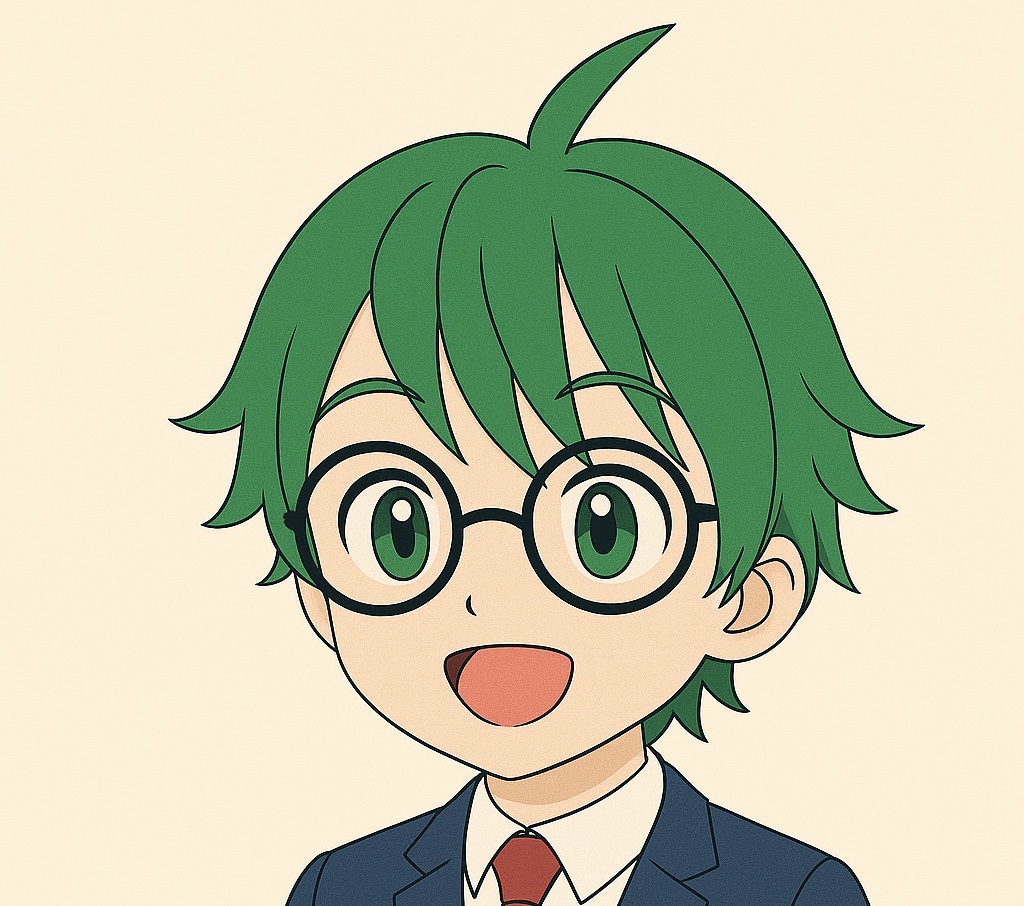
一般病棟に出てきても、まだ油断しちゃダメだよ!
どうして、心臓手術後に心房細動が起こりやすいの?
結論から言うと、
原因はひとつではありません。
心臓手術後は、
👉 いくつかの要因が重なって
心房細動が起こりやすくなっていると考えられています。
- 心房へのダメージ
- 体のバランスの乱れ
- 心房にかかる負荷
これらが重なって、
心房細動が起こりやすい状態になります。
理由① 心房が手術のダメージを受けている
心臓手術後は、
心臓全体に大きな負荷がかかっています。
その影響は、心房にも及びます。
その結果、
- 心房の電気の流れが乱れやすくなる
- 電気的に不安定な状態になる
といった変化が起こりやすくなります。

心臓を治すための手術だけど、
心房にとっては“かなりの刺激”なんだねー
理由② 自律神経・体のバランスが乱れやすい
術後は、体の中でさまざまな変化が同時に起こります。
- 痛み・ストレス・発熱・睡眠不足
→ 自律神経のバランスが乱れやすい - 輸液量の変化、利尿薬の使用、出血や脱水
→ 体液バランスや電解質(K・Mgなど)が乱れやすい
こうした影響が重なり、
心房細動が起こりやすい状態になります。
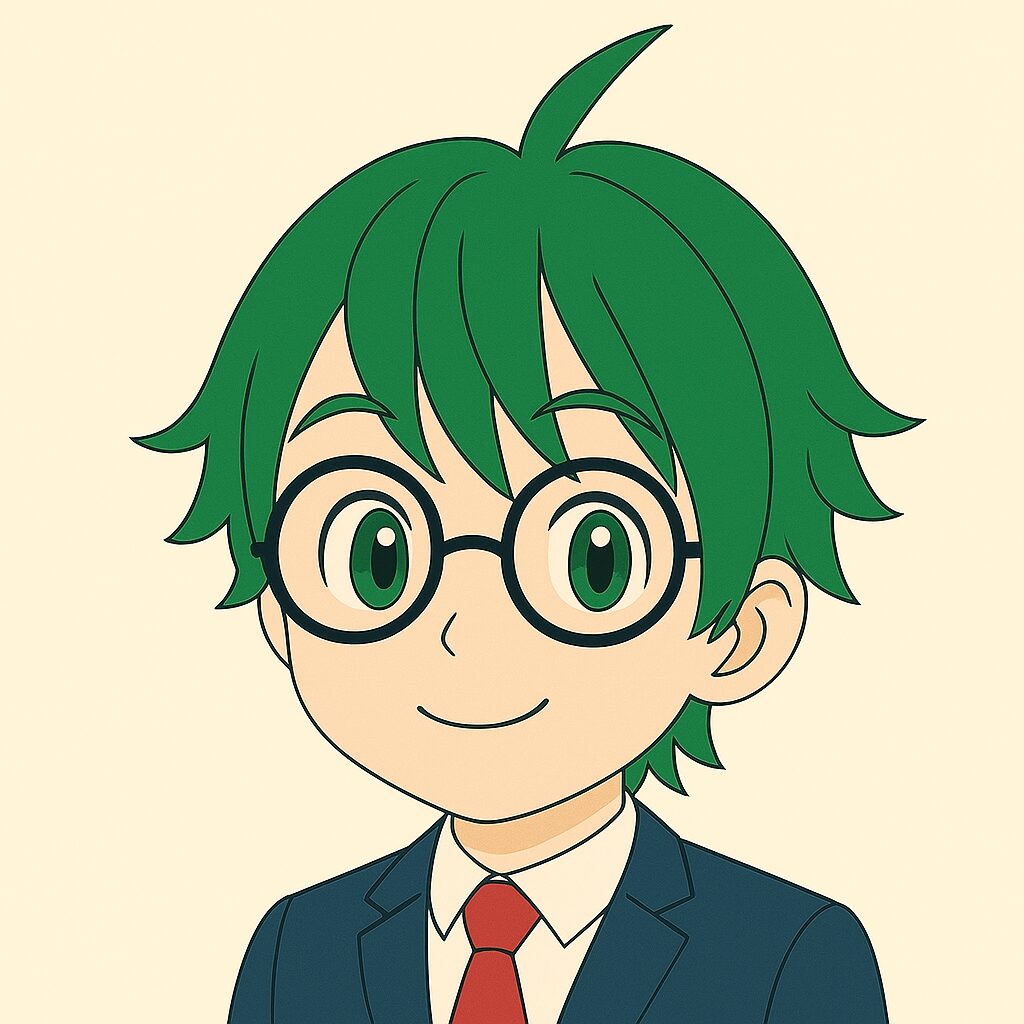
体が回復しようとして、
体の中ではいろいろバタバタしてる状態なんだ
理由③ 心房に負荷がかかり、引き伸ばされやすい
術後は、
- 体液量の変化
- 心機能低下によるうっ血
- 心臓の中の圧の変化
などの影響で、
心房に負担がかかりやすくなります。
心房が引き伸ばされると、
- 電気刺激がきれいに伝わらなくなる
- リズムが乱れやすくなる
その結果、
心房細動が起こりやすくなると考えられています。

なるほど〜。
心房へのダメージや体の変化が重なって、
心房細動が出やすくなってるってことなんだね
脱水が引き金?現場で多い心房細動の原因
ここからは、
循環器病棟でよくある“あるある視点”のお話です。
集中治療室(ICU)から一般病棟へ移ってくると、
- 持続点滴が減る、または終了する
- 内服の利尿薬が開始される、もしくはすでに内服している
(フロセミド、スピロノラクトン、サムスカ など)
……という状況になっていきますよね。
このタイミングで、
気づかないうちに
脱水が原因で心房細動が起こる!
というケースを、私は何度も見てきました。
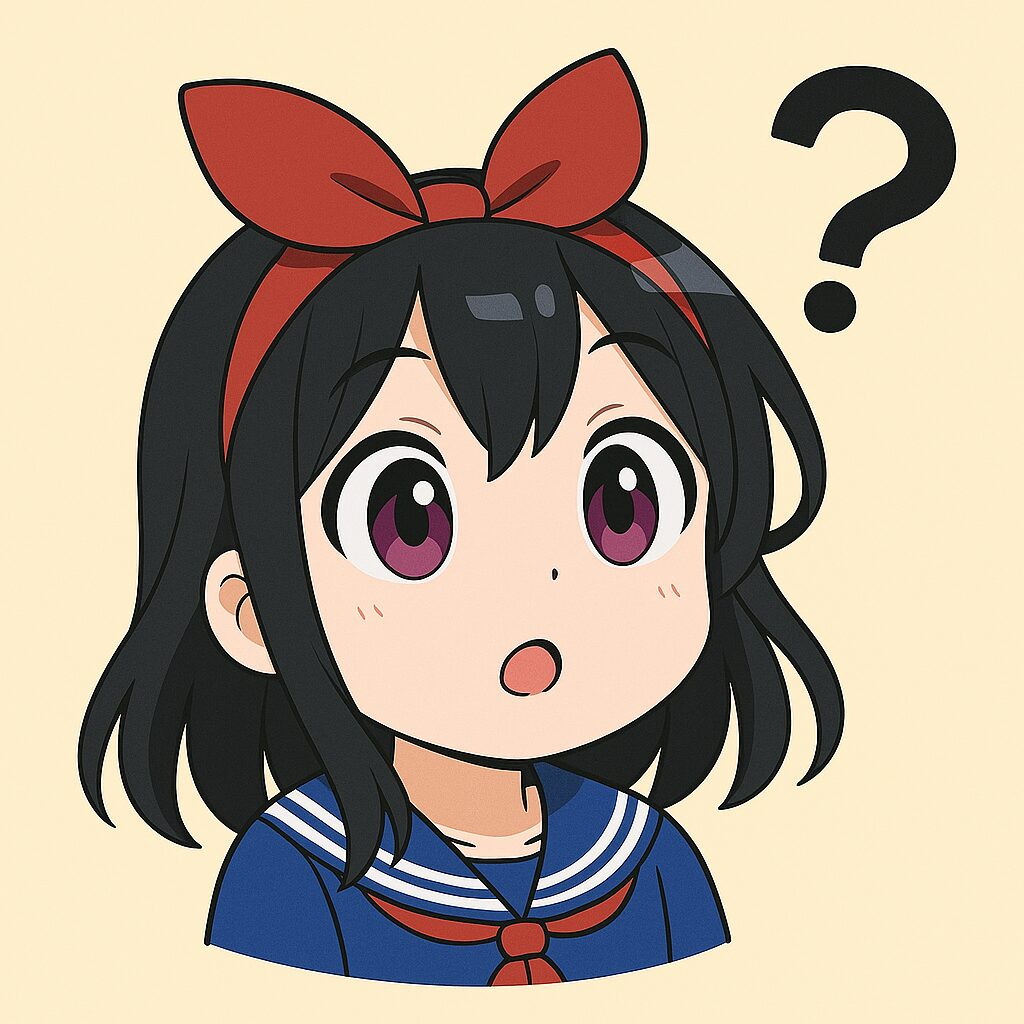
なんで脱水で心房細動になるの?
脱水になると、
知らないうちに心臓に負担がかかる状態になります。
- 体の水分が減り、血液が濃く(ドロドロに)なる
- 濃い血液を送るため、心臓がいつもより頑張って働く
- その結果、心房に余計な負担がかかりやすくなる
また、脱水や利尿薬の影響で、
カリウム(K)やマグネシウム(Mg)といった、心臓のリズムを保つ電解質が乱れやすくなる。
結果として…
電解質が乱れ、心房に負担がかかることで、
心臓の電気の流れが不安定になり、
心房細動が起こりやすくなるのです。
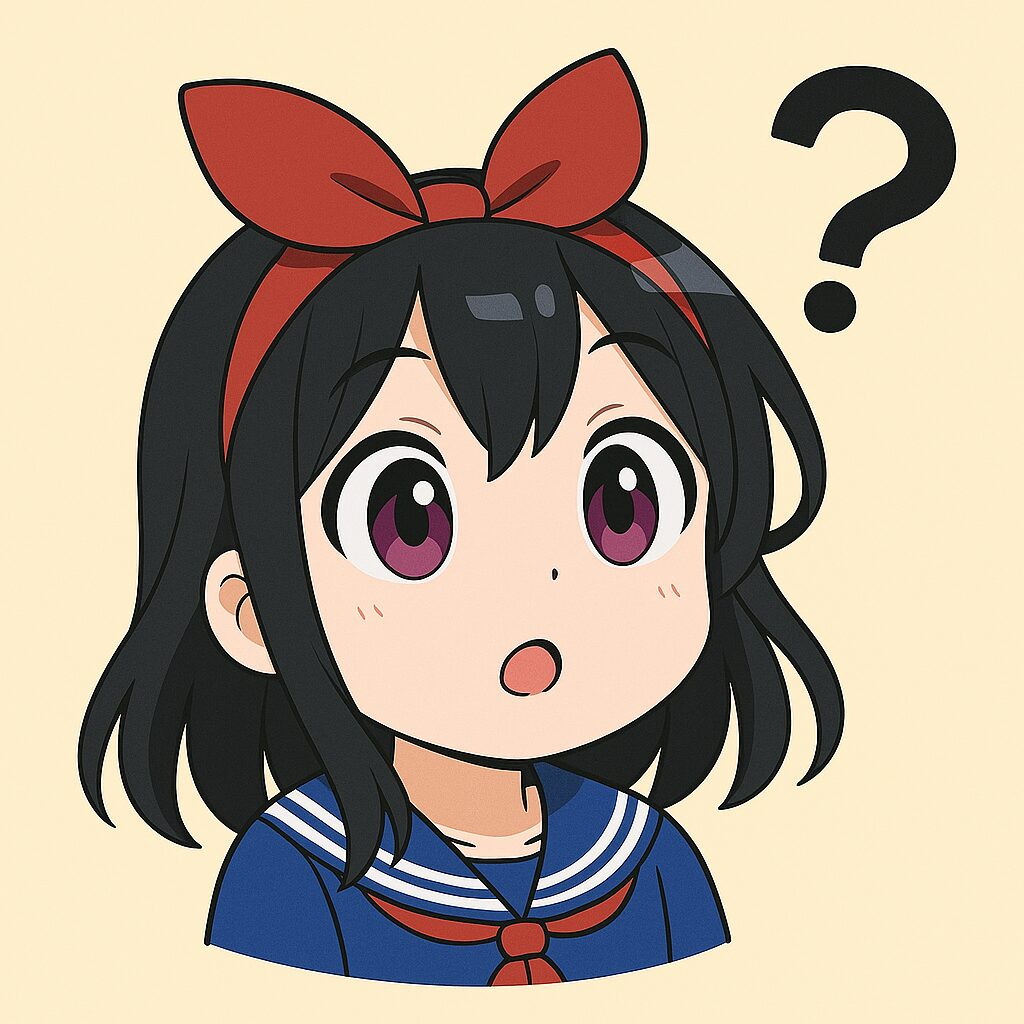
どうして脱水になるの?
理由はとてもシンプルで、
利尿薬で水分はたくさん外に出ている(=おしっこは増える)のに、
水分をあまり飲まないからです。

なんで水分をとらなくなるの?
患者さんに話を聞いてみると、
理由はだいたいこんな感じです。
- 動くと術後の傷が痛い
- トイレの回数が増えるのが嫌
- そもそも、あまり喉が渇かない
こうした理由が重なって、
- 水分摂取量が少ない
- 利尿薬で水分はどんどん出ていく
という状態になり、
気づかないうちに水分量が減ってしまい、
脱水をきっかけに心房細動が起こるケースは、実はとても多いです。
特に、
点滴が減ったあと・終了したあとは、
食事がとれていても、水分が足りていないことはよくあります。
だからこそ、
- 水分をちゃんと飲んでいるか
- 尿量は少なくなっていないか
そんな視点を持つことが、
心房細動を防ぐ大事なポイントになります。
心房細動を早く見つけるために、意識していたこと
洞調律から心房細動へ移行する変化は、
できるだけ早く気づけた方が安心ですよね。
でも実際の現場では、
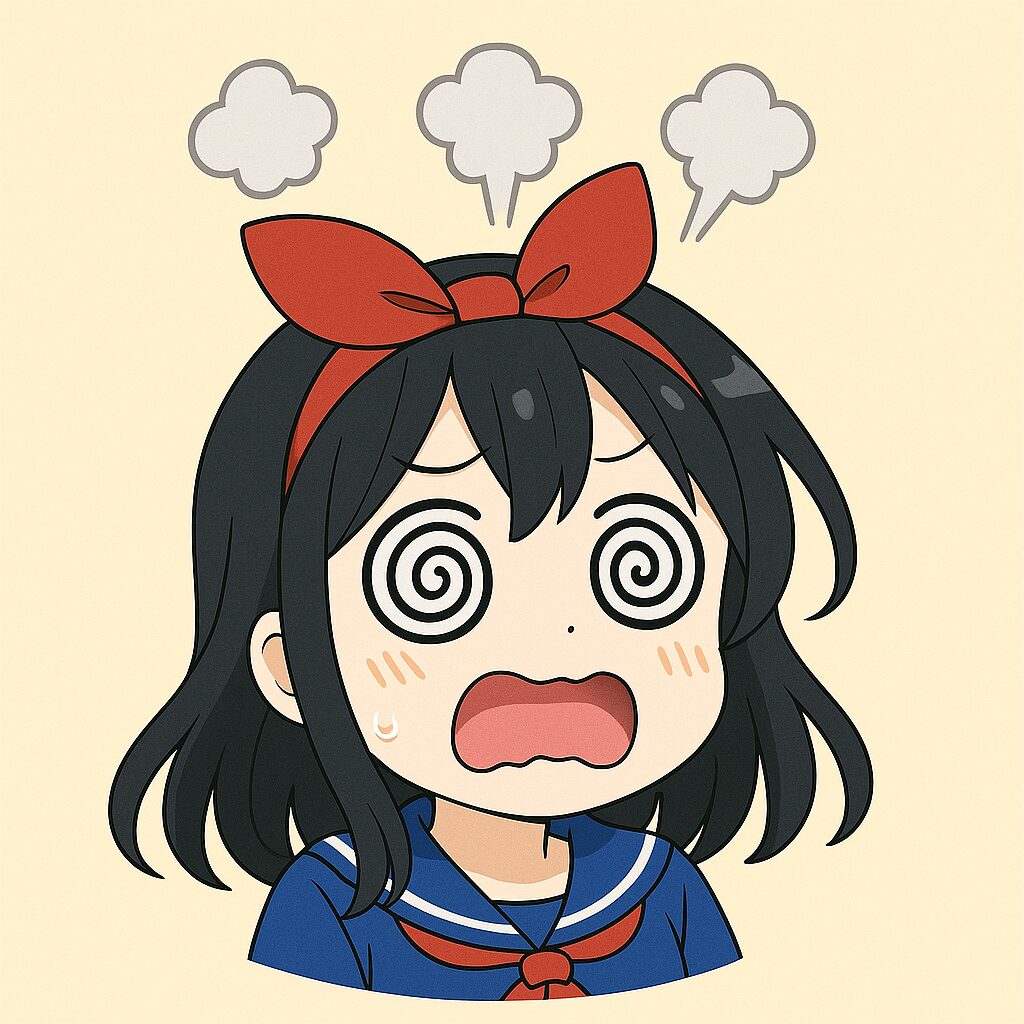
忙しいし、受け持ち患者さんも多いし、モニターをゆっくり見る余裕がないよ〜……
…という状況も多いと思います。
本当は、
1時間に1回はモニターをチェックできるのが理想ですが、
現実的にはなかなか難しいですよね。
時間がないときに、私が意識していたこと
そんな中で私が実践していたのは、
「最低限、頻脈になっていないかだけは見る」という方法です。
心房細動に移行すると、
👉 頻脈になることが多い
という特徴があります。
実際にやっていたこと
- 勤務はじめに
👉 モニターの波形と心拍数をメモ
(特に心臓手術後の患者さんは要チェック) - モニター前を通るときに
👉 チラッと心拍数だけ確認 - 心拍数が上がっていないかを意識する
特に、
心拍数が120回/分を超える頻脈は
アラーム設定されていることも多いので、
音にも注意していました。
モニターが見られなくても大事なこと
忙しくて波形をじっくり見られないときでも、
👉 アラーム音には必ず注意を払う
これはとても大切です。
心房細動だけでなく、
- 徐脈
- 心室頻拍(VT)
- 心室細動(VF)
といった緊急性の高い不整脈が
起きている可能性もあります。
もちろん、
心房細動に移行しても頻脈にならないケースもあります。
なので、
落ち着いたタイミングで
モニターをじっくり見る時間を作ることは大前提です。
それでも、
「時間がなくて全部は見られない…」
という看護師さんは、
まずは
👉 心拍数の変化(特に頻脈)に注目する
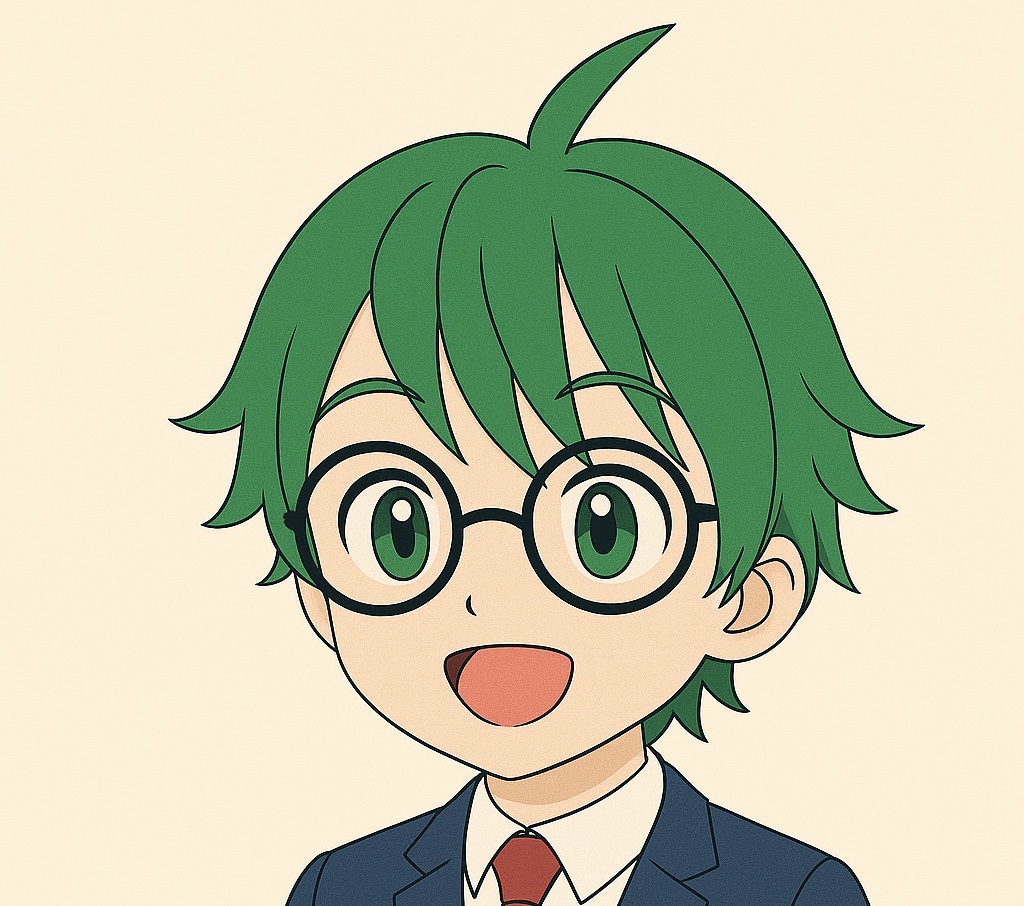
この視点だけでも、
心房細動の早期発見につながりますよ。
心房細動ってどういう状態?
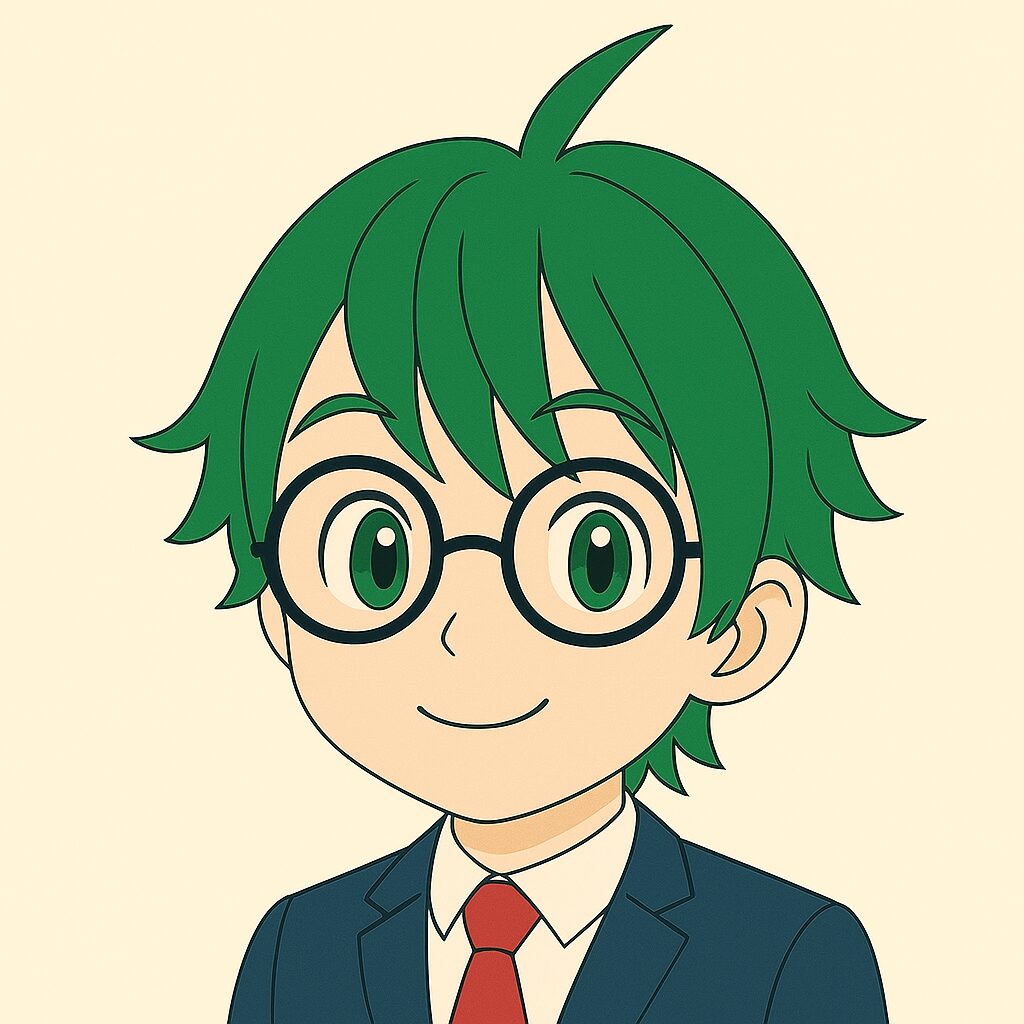
心房細動(AF)は、
心臓のリズムがバラバラになってしまう不整脈です。
本来、心臓は
洞結節(どうけっせつ)という「司令塔」からの指示で動いています。

- 洞結節がリズムを作る
- 心房がその指示を受け取る
- 心室へ一定のリズムで伝わる
この流れが保たれていると、
心臓は規則正しく働くことができます。
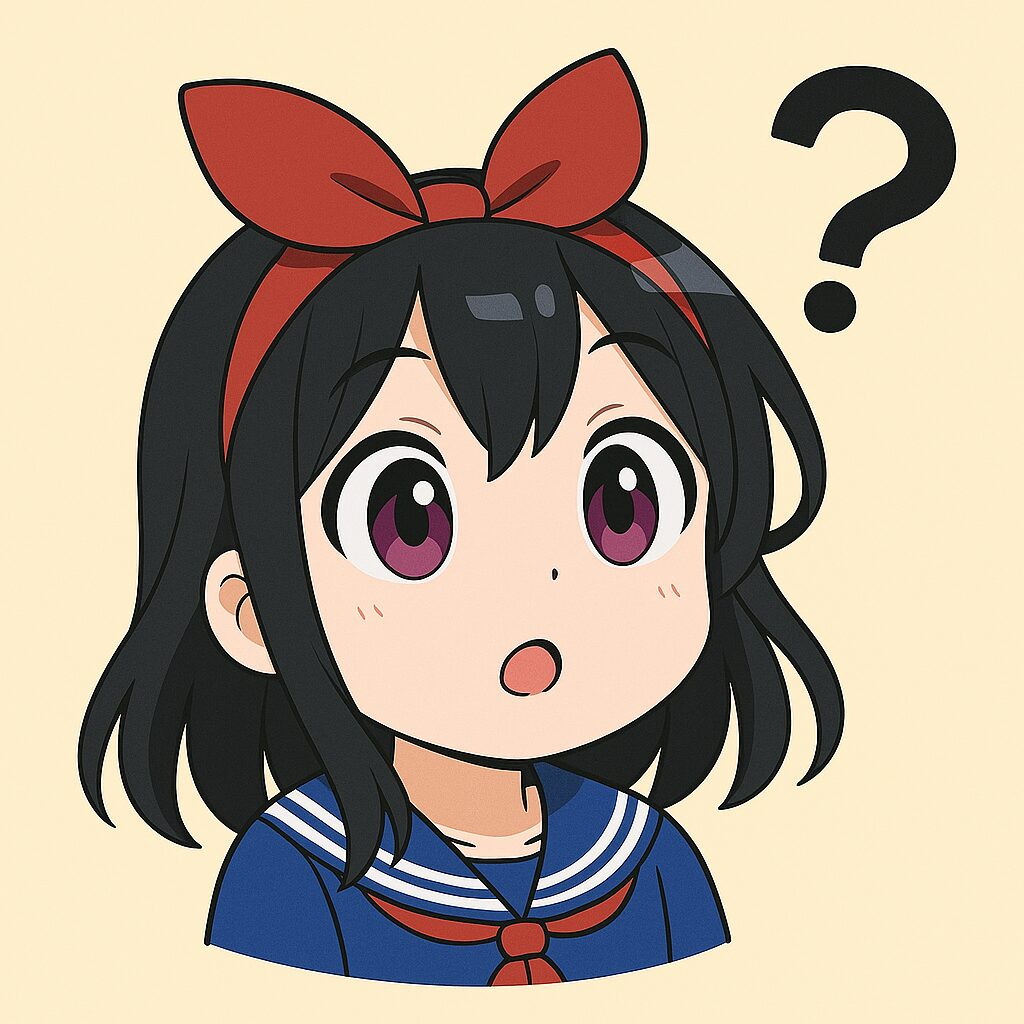
じゃあ、心房細動だとどうなるの?
心房細動では、
洞結節からの指示がうまく伝わらなくなります。
代わりに、心房にいる細胞たちが
それぞれ勝手に電気信号を出し始め、
心房の中が大混乱の状態になります。

- 司令塔(洞結節)の声が届かない
- 心房の細胞が好き勝手に指示を出す
- 心房がバラバラに動く
心房細動では、
心房の中で1分間に約250〜350回もの電気信号が発生しています。
通常の心房は、
1回の拍動ごとに、しっかり収縮して血液を送り出す
のですが、心房細動になると、
あまりに速く指示が出るため、1回1回しっかり収縮することができず、細かく震えるような動きになってしまいます。
この様子から
「心房が細かく動く=心房細動」と呼ばれています。
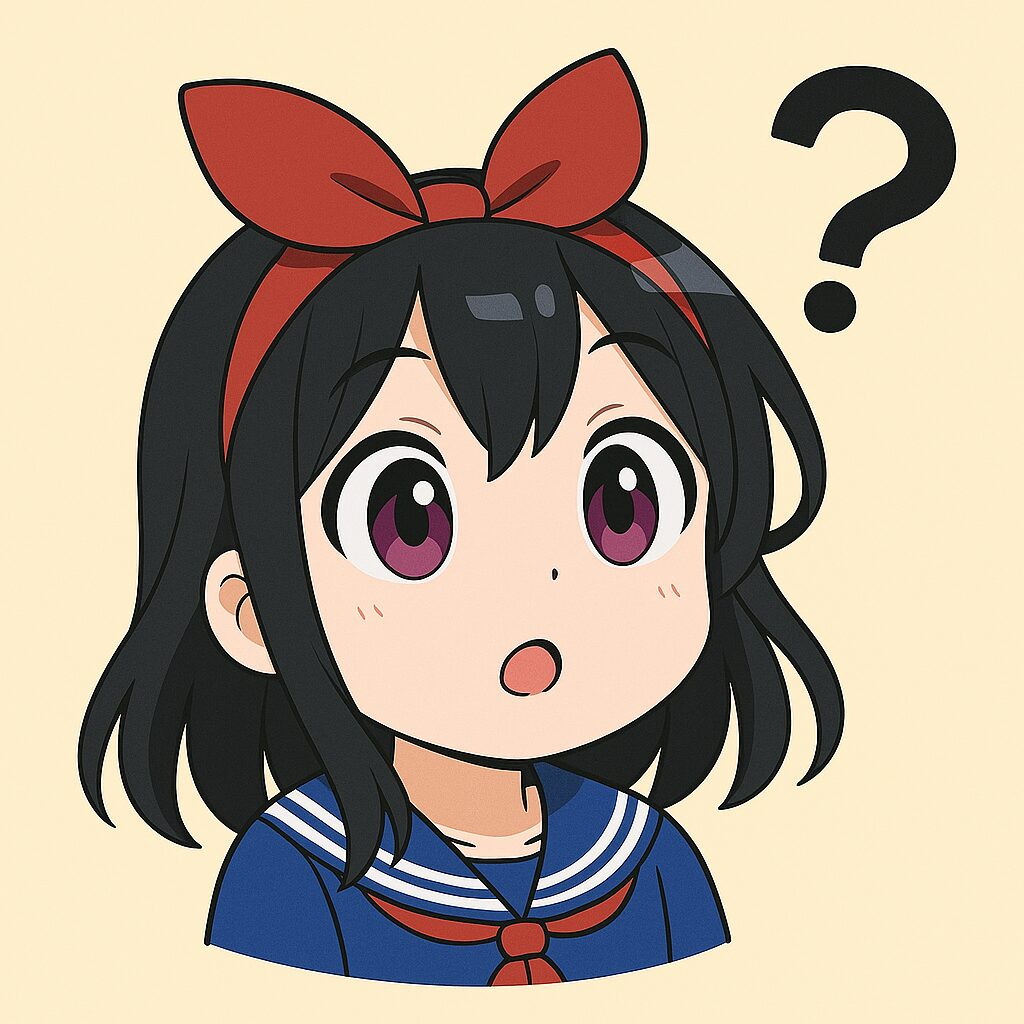
心房が細かく動くとどうなるの?
心房が細かく震えるように動くことで、
心房の中で大量の電気信号が発生し、
一部が不規則に心室へ伝わることで、
- RR間隔がバラバラ
- 脈が不規則
- 心拍数が100回/分以上の頻脈になりやすい
という特徴が出ます。
つまり心房細動とは、
洞結節の司令が効かなくなり、
心房の細胞が暴走している状態。
その結果、脈が不規則で速くなりやすい不整脈です。
徐脈なのに心房細動のこともある
心房細動(AF)と聞くと、
- RR間隔がバラバラ
- 心拍数が速い(頻脈)
というイメージを持つと思います。
実際、心房細動は心拍数が100回/分以上になることが多い不整脈です。
ですが時々、
「徐脈なのに、実は心房細動」
という、少し分かりにくい波形に出会うことがあります。
一見すると心房細動に見えない波形
このときの心電図には、次のような特徴があります。

- P波が見えない
- RR間隔は一定
- 心拍数は遅い(徐脈)
- QRS幅が広い
RR間隔も整っていて、脈も遅い。
そのため、

心房細動ではなさそう?
でも、じゃあ何の波形…?
と、現場で迷いやすい波形になります。
この状態の正体は、
心房細動 + 3度房室ブロック(完全房室ブロック)
という、2つの不整脈が合わさった状態です。
3度房室ブロックってなに?
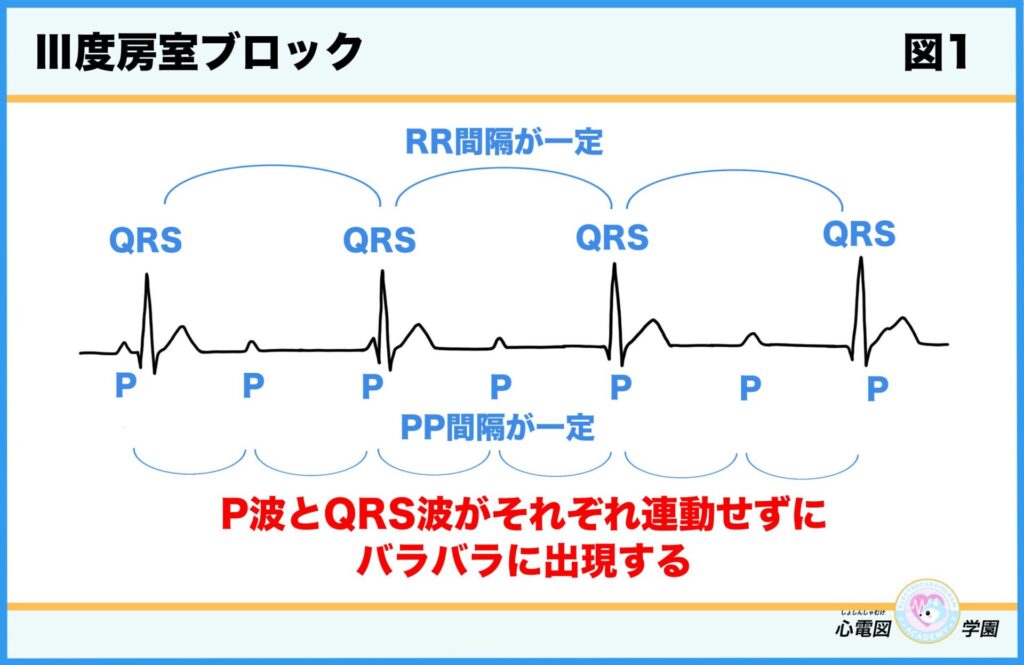
3度房室ブロックとは、
- 心房で発生した電気信号が
- 房室結節で完全に遮断され
- 心室に1つも届かなくなる状態
※ 房室結節とは、心房から心室へ電気を伝えるための「中継地点」のこと。
つまり、
心房と心室が、まったく連絡を取れなくなる状態
です。
心室に連絡がいかなくなると、心臓は止まるの?
いいえ。
心室には、
「上から指示が来ないなら、
自分で動かないと生きられない」
という安全装置のような仕組みがあります。
そこで起こるのが
心室補充収縮(しんしつほじゅうしゅうしゅく)です。
心室補充収縮とは?
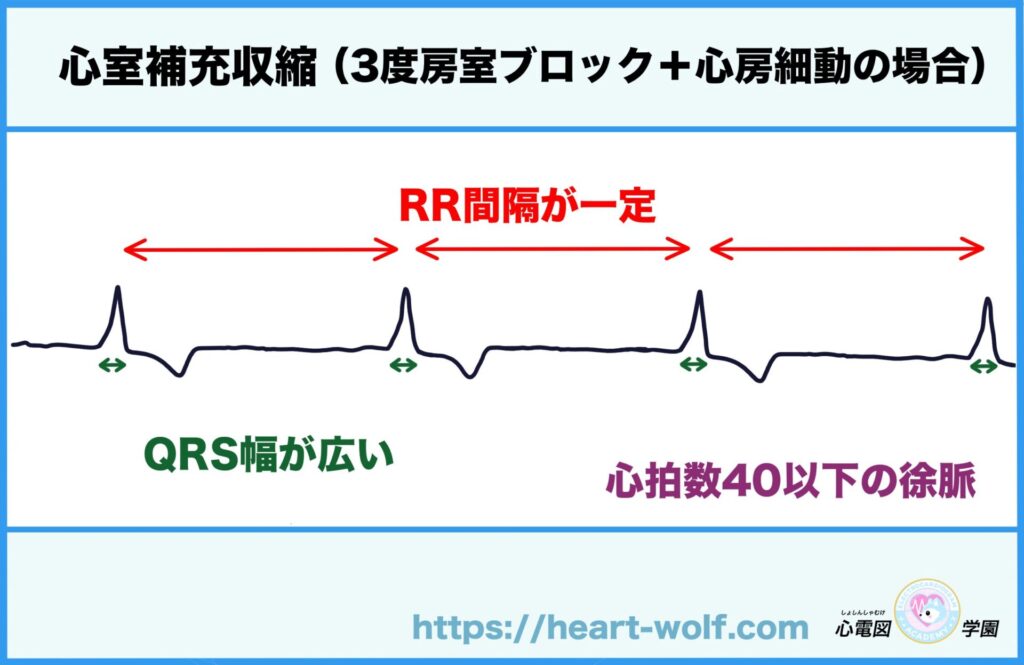
心室補充収縮は、
- 洞結節や心房の指示とは関係なく
- 心室が自分で作ったペースで
- 最低限の拍動を保っている状態
を指します。
心室補充収縮の特徴
心室補充収縮には、次の特徴があります。
- 心拍数がとても遅い
→ 多くは 40回/分以下 - RR間隔は基本的に一定
- QRS幅が広くなる
なぜ徐脈なのに心房細動になるの?
心房細動 + 3度房室ブロック、この2つが合わさると、
- 心房:心房細動
→ P波がなく、心房内はバラバラに動いている - 房室結節:完全にブロック
→ 心房の電気は心室に届かない - 心室:補充収縮
→ 規則正しいけれど、とても遅い拍動。QRS幅が広い。
という状態になります。
その結果、

- P波はない
- RR間隔は整っている
- QRS幅が広い
- 徐脈
という、
一見すると心房細動に見えない波形になるのです。
心房細動 + 3度房室ブロックには注意!
この波形は、
心房細動単独よりも重症度が高い
不整脈です。
特に、
- めまい
- ふらつき
- 失神
- 血圧低下
などの症状がある場合は、
ペースメーカー挿入などの処置が必要になることもあるため、すぐに報告が必要です。
また、
心房細動+3度房室ブロックは
ジギタリス製剤(主にジゴシン)の過量投与でも起こることがあるため、
👉 何を内服しているかの確認も重要です。

今回はここまで!おつかれさまでした〜
完璧じゃなくていいんです。ゆっくり覚えていきましょう!
- 心電図のみかた、考え方【基礎編】杉山裕章 著
- 心電図のみかた、考え方【応用編】杉山裕章 著
- レジデントのためのこれだけ心電図 佐藤弘明 著
- これならわかる!心電図の読み方 大島一太 著
- 心電図の読み方パーフェクトマニュアル 洋土社
- ハート先生の心電図レクチャー基礎編 市田聡 著
- 『胸部外科手術における術後心房細動』(横田泰佑,2018年)
- 『冠動脈バイパス術後心房細動の予防と治療』(冠疾患誌 2015/尾澤直美・下川智樹)